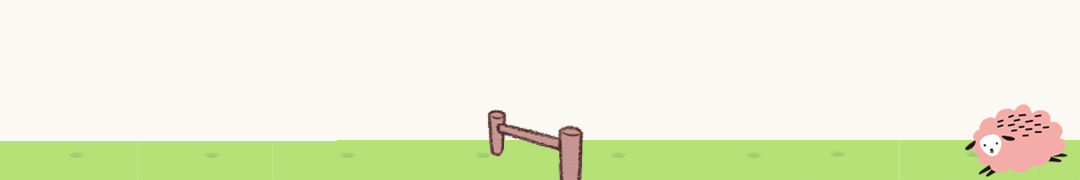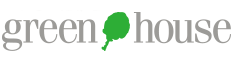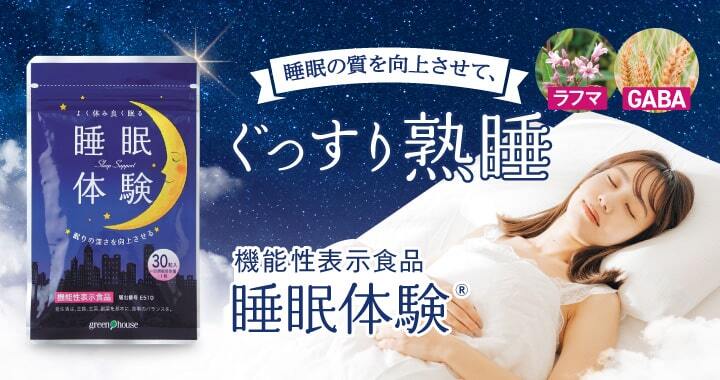寝ても疲れがとれない5つの原因 | ストレス・自律神経乱れ・睡眠の質を解説
最終更新日:2025.05.26

「しっかり寝たはずなのに、朝からダルい」「何時間寝ても疲れがとれない」。
そんな状態が続いていませんか?
睡眠時間を確保しているのに疲れが残るのは、単なる寝不足ではありません。
自律神経の乱れ・ストレス・睡眠の質の低下といった、“見えにくい不調”が背景にあるケースが多いのです。
この状態を放っておくと、
・朝起きられない
・仕事や家事の集中力が続かない
・気分が落ち込む
など、日常生活にまで支障が出てしまいます。
本記事では、特に20代〜40代に多い「寝ても疲れがとれない原因」を、5つに分けて徹底解説。
さらに、今日から取り入れられるセルフケアや、忙しい人でも無理なく続けられる対策法までご紹介します。
「なんとなく疲れが抜けない…」と感じているなら、まずは原因を知ることから始めてみましょう。

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
睡眠栄養指導士
小田 健史
健康食品業界で数々の商品開発や販促に12年以上携わる。
睡眠不足に悩まされ続けた自身の不眠体験から、一念発起して「睡眠栄養指導士」の資格を取得し、自らの知識と経験を基に機能性表示食品に登録された睡眠向上サプリ「睡眠体験」を開発。
現在、睡眠栄養指導士として多くの悩める方々へ睡眠の改善に関する情報を発信中!
<資格>
・一般社団法人 睡眠栄養指導士協会
睡眠栄養指導士® 中級
パーソナル睡眠アドバイザー®
・特定非営利活動法人 日本成人病予防協会
健康管理士 一般指導員
目次
寝ても疲れがとれない原因は?主な5つの要因
「寝ても疲れがとれない」「朝からずっとだるい」。
単なる寝不足だと思っていると、見逃してしまう重大なサインが隠れていることもあります。
実は、疲労が抜けない背景には、自律神経の乱れや睡眠の質の低下、ストレスや栄養の偏りなど、現代人ならではの原因が潜んでいます。
ここでは、睡眠をとっても疲労感が残る主な5つの要因について、わかりやすく解説します。
自分に当てはまるポイントがないか、ぜひチェックしてみてください。

1. 自律神経の乱れ
人の体は、自律神経によって内臓や血管、体温、ホルモン分泌などがコントロールされています。
通常は日中に交感神経、夜間に副交感神経が優位になりますが、ストレスや生活の乱れによってこの切り替えがうまくいかなくなることがあります。
交感神経が夜も働き続けると、心身は緊張したまま。
その結果、深い眠りに入りにくくなり、「寝たはずなのに疲れが残る」状態が続いてしまいます。
2. 睡眠の質が低い
長く寝れば疲れがとれるわけではありません。
大切なのは「深く眠れているかどうか」です。
・寝つきが悪い
・夜中に何度も目が覚める
・朝起きた瞬間からだるい
こうした状態が続いているなら、睡眠の質が落ちているサイン。
寝る前のスマホ使用やカフェイン摂取、寝室の明るさ・温度・騒音など、環境要因が影響しているケースも多々あります。

3. ストレスや精神的な疲労
精神的ストレスは、肉体的な疲労よりも回復に時間がかかるといわれています。
・仕事や人間関係のプレッシャー
・仕事や家事、育児などのバランス
・将来への不安
など、20代~40代は慢性的なストレスを抱えやすい年代です。
ストレスによって交感神経が過剰に働くと、心身のリラックスが妨げられ、夜の休息にも影響を及ぼします。
4. 栄養不足・生活リズムの乱れ
偏った食事や不規則な生活も、疲労感を引き起こす大きな要因です。
コンビニ食や外食が中心の生活では、ビタミンB群や鉄、マグネシウムなどの栄養素が不足しやすく、エネルギーの代謝がスムーズに行われません。
また、毎日の就寝・起床時間がバラバラだったり、寝る直前までスマホを見ていたりすると、睡眠の質にも悪影響を及ぼします。

5. 隠れた病気の可能性
慢性的な疲労の影に、病気が潜んでいるケースも。
・甲状腺機能低下症
・鉄欠乏性貧血
・慢性疲労症候群
などが代表的な疾患です。
生活習慣を見直しても改善が見られない場合は、医療機関に相談するのが安心です。
【年代別】疲れがとれない悩みと特徴
「なぜか最近、疲れがとれにくい気がする」。
その感覚、実は年齢による体の変化が影響しているかもしれません。
20代・30代・40代と、ライフステージが変わるにつれて、ストレスの内容や体調の悩みも変化していきます。
仕事の責任、家庭との両立、ホルモンバランスの変化など、それぞれの年代に特有の疲れの原因があるのです。
ここでは、年代別に見られる「疲れがとれない悩み」の特徴を詳しく紹介します。
今の自分の状態を知ることで、適切な対策が見えてくるはずです。

20代のケース
学生から社会人へと大きく環境が変化する時期であり、不安定な生活リズムや精神的ストレスが疲労感の原因に。
また、自律神経が乱れやすく、寝つきが悪くなるケースも少なくありません。
30代のケース
働き盛りで責任が増え、ストレスの蓄積がピークに達する年代。
育児や家庭との両立で心身のリカバリーが追いつかず、慢性的な疲労感を感じる人が増えてきます。
40代のケース
加齢に伴いホルモンバランスが変化し、回復力の低下や「疲れが抜けにくい」感覚が強まる時期です。
さらに睡眠の質も徐々に落ちていくため、より意識的なケアが求められます。
今日からできる!疲れをとるためのセルフケア5選
「疲れをとりたい。でも何をすればいいかわからない」。
そんな方にこそ試してほしい、今日から無理なく始められるセルフケア法をご紹介します。
どれも手軽で継続しやすいものばかりですので、今夜から試してみてくださいね。
1. “耳ほぐし”で自律神経ケア
耳を軽く引っ張ったり、ゆっくり回したりするだけで、自律神経に関わる迷走神経が刺激され、リラックス効果が期待できます。
寝る前に1〜2分行うだけで、気持ちがスッと落ち着き、入眠しやすくなる人も多いセルフケアです。

2. 起床後の“白湯”習慣
朝に白湯を1杯飲むと、内臓が温まり代謝が活性化します。
胃腸がゆっくり動き出すことで、自律神経も整いやすく、1日のスタートがラクになります。
白湯には体を目覚めさせる“スイッチ”の役割も。
3. 日中に「笑う」時間をつくる
笑いは副交感神経を優位にし、ストレス軽減や免疫力向上にもつながる天然のリラックス法。
お笑い動画や漫画など、ほんの5分でも「笑える時間」を意識的に持つことで、心身の疲れを軽減しやすくなります。

4. 寝る1時間前は“ブルーライト断ち”
スマホやPCの画面から出る光(ブルーライト)は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を妨げます。
意識して1時間前から画面を見ないようにすると、自然な眠気が促され、睡眠の質が改善されやすくなります。
5. 手軽な睡眠サポートアイテムの活用も選択肢に
「生活改善を意識しているけど、思うように続かない」「すぐに効果を実感したい」。
そんな方には、睡眠の質を高めるためのサポートサプリメントの活用もひとつの手です。
例えば、
・自律神経の乱れをサポートする成分
・ぐっすり眠れるよう整える栄養素
などが含まれたものを、寝る前のルーティンに組み込むことで、忙しい人でもムリなく継続しやすくなります。

毎日の睡眠をぐっと変える!人気の睡眠サポート成分配合サプリ >>詳しく見る
まとめ | 寝ても疲れがとれない原因と効果的な対策を理解しよう
「寝ても疲れがとれない」と感じるときは、単なる寝不足だけでなく、体の中で複数の要因が絡み合っていることが多いものです。
特に、以下の5つのポイントは疲労が抜けない根本原因として見逃せません。
・自律神経の乱れ
・睡眠の質の低下
・精神的ストレス
・栄養バランス・生活リズムの乱れ
・加齢による体質変化
これらをしっかり理解したうえで、自分に合った生活習慣の改善やセルフケアを取り入れることが、疲労回復の第一歩です。

毎日の忙しさで生活改善が難しい場合は、睡眠の質を手軽にサポートするアイテムの活用も賢い選択肢となります。
一歩ずつ無理なく実践を重ねることで、体調は確実に変わり始めます。
「今日からできること」をスタートし、疲れに悩まない毎日を取り戻しましょう。
よくある質問 | 寝ても疲れがとれない時のQ&A
また、生活リズムや睡眠の質が気になる方は、こちらの睡眠サポートサプリも参考になります。