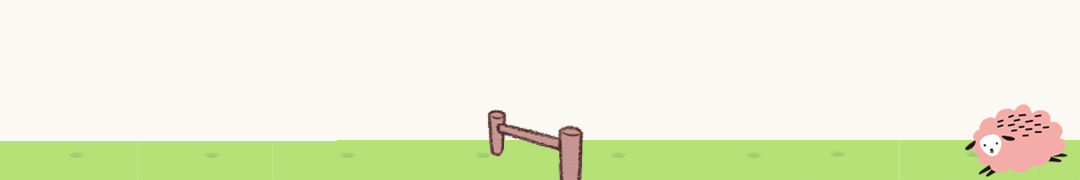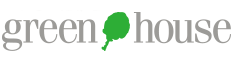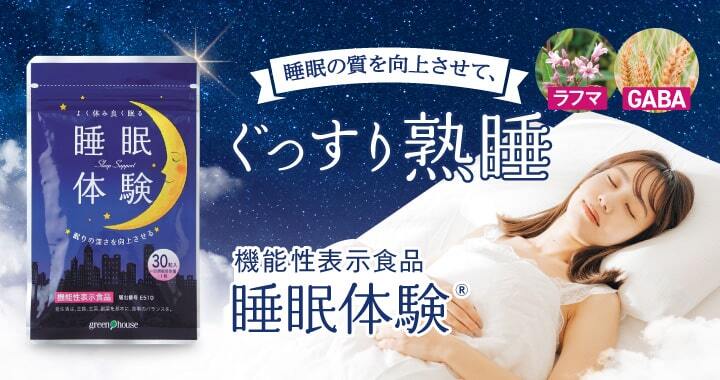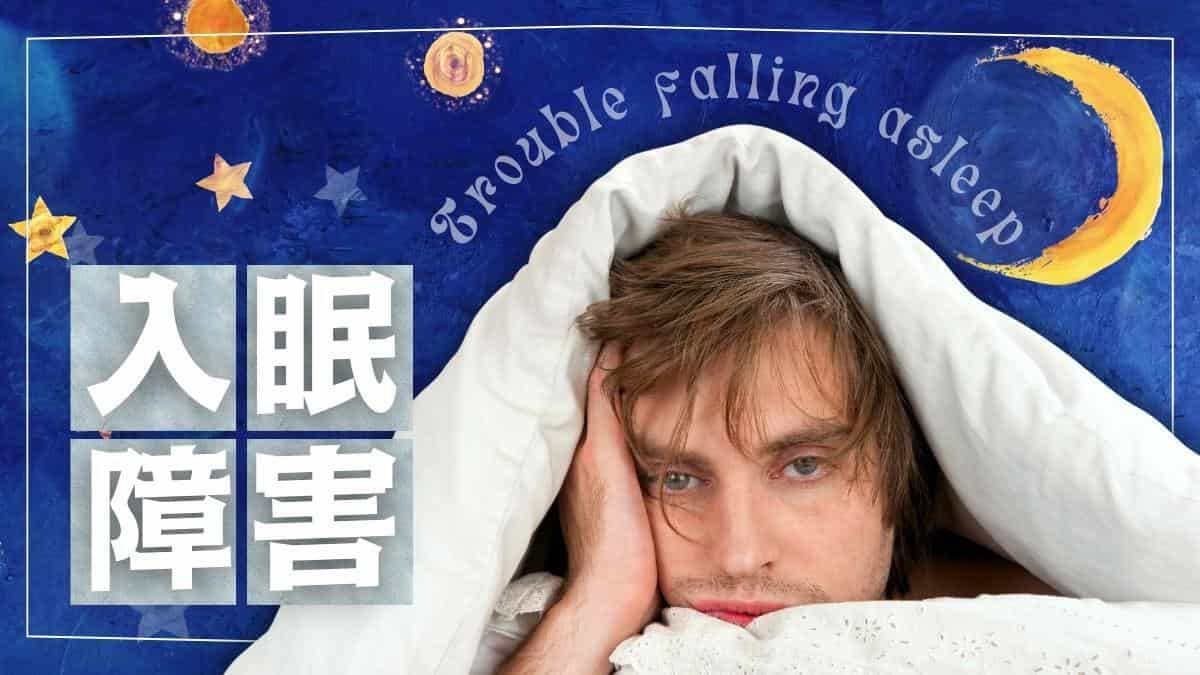足がむずむずして眠れない?それ「むずむず脚症候群」かもしれません|原因と今すぐできる対策
最終更新日:2025.5.01

「足がむずむずして眠れない」「布団に入ると足の奥がムズムズして、動かさずにいられない」。
こんな症状に心当たりがある方は、「むずむず脚症候群(RLS)」かもしれません。
むずむず脚症候群になると、慢性的な睡眠不足による日中の集中力の低下や、メンタルの不調を引き起こす可能性も。
この記事では、むずむず脚症候群の原因やチョコレートとの意外な関係、改善のために役立つ食べ物や習慣、そして睡眠の質を高めるための対処法まで、詳しく解説していきます。

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
睡眠栄養指導士
小田 健史
健康食品業界で数々の商品開発や販促に12年以上携わる。
睡眠不足に悩まされ続けた自身の不眠体験から、一念発起して「睡眠栄養指導士」の資格を取得し、自らの知識と経験を基に機能性表示食品に登録された睡眠向上サプリ「睡眠体験」を開発。
現在、睡眠栄養指導士として多くの悩める方々へ睡眠の改善に関する情報を発信中!
<資格>
・一般社団法人 睡眠栄養指導士協会
睡眠栄養指導士® 中級
パーソナル睡眠アドバイザー®
・特定非営利活動法人 日本成人病予防協会
健康管理士 一般指導員
目次
むずむず脚症候群(RLS)とは?症状と特徴を知ろう
むずむず脚症候群(Restless Legs Syndrome: RLS)は、じっとしているときに足の内部に不快な感覚が生じ、動かさずにはいられなくなる神経系の障害です。
不快感は脚を動かすことで一時的に和らぎますが、寝ようとするたびに症状が現れるため、「眠れない夜」が慢性化してしまうのです。

むずむず脚症候群の症状の特徴
・主に夜間、寝る前や静かに座っているときに発症
・足の内部がムズムズする、チクチクするような違和感
・動かすと一時的に症状がやわらぐ
・睡眠障害につながることも多い
むずむず脚症候群になりやすいのはどんな人?
日本では人口の2~3%が罹患していると推測され、特に40代以降の女性に多い(男性の1.2~1.4倍)ことが分かっています(※)。
※田中章郎, et al. "2. 最近の新薬の適正使用―インクレチン製剤, 生物学的製剤などについて―." 日本透析医学会雑誌 45.2 (2012): 120-123.

むずむず脚症候群の原因とは?ストレス?血のめぐり?
むずむず脚症候群の原因は完全には解明されていません。
しかし、以下の要因が発症に関連していると考えられています。
1.鉄分不足
鉄は脳内の神経伝達物質「ドパミン」の合成に関与しています。
ドパミンのバランスが崩れると、脚の違和感や興奮状態が起きやすくなります。
特に「隠れ貧血(血液検査では正常だが、フェリチン値が低い状態)」の人は要注意です。
2.カフェインやアルコールの摂取
実は、夜に食べる「チョコレート」も要注意。
チョコレートには微量のカフェインが含まれており、脳を刺激し、神経を過敏にします。
さらに、夜にお酒を飲む習慣がある人も注意が必要です。
アルコールは眠りを浅くし、むずむず感を悪化させるリスクがあります。

3.慢性疾患や妊娠
糖尿病、腎不全、パーキンソン病、妊娠中のホルモン変化などが関連することもあります。
これらの背景がある場合、医師の診断を受けた上での対処が必要です。
チョコレートはなぜむずむず脚症候群と関係するの?
「チョコレートに含まれるカフェインが、むずむず脚症候群の原因」と聞くと「それなら、同じようにカフェインが含まれるコーヒーや紅茶も原因になるのでは?」と思うかもしれません。
確かに、カフェインはどの食品にも一定の影響を及ぼします。
しかし、むずむず脚症候群において“チョコレート”が特に注目される理由は、以下の3つの要因が重なっているからです。
1.鉄の吸収を妨げる性質がある
チョコレート(特にダークチョコレート)に含まれるカカオポリフェノールやカルシウムは、体内への鉄分の吸収を阻害することがあります。
鉄分が足りない人がチョコレートを習慣的に食べていると、鉄の吸収が妨げられ、結果的に症状が悪化しやすくなる可能性があります。
2.糖分と脂肪分による神経刺激
チョコレートは高脂肪・高糖質な食品です。
この組み合わせの食べ物は血糖値の急上昇・急降下を引き起こしやすく、自律神経に影響して、神経の興奮やむずむず感を悪化させることがあります。
3.カフェインの“無自覚摂取”が起こりやすい
特にハイカカオチョコレートでは、板チョコ1枚に50〜70mg以上のカフェインが含まれていることもあります。
コーヒーであれば「カフェインを摂った」と意識できますが、お菓子として気軽に口にするチョコレートでは、無自覚のうちにカフェインを過剰摂取してしまうことが少なくありません。

むずむず脚症候群の人はチョコレートは完全NG?
しかし、むずむず脚症候群の人がチョコレートを完全に避けるべきというわけではありません。
摂取のタイミングと量に注意すれば、リスクを減らすことが可能です。
・午後3時以降は控える
・寝る直前は避ける
・食べるなら低糖質・低カフェインのタイプを選ぶ
むずむず脚症候群の改善の鍵は「鉄分」と「睡眠の質」
むずむず脚症候群の根本的な改善において最も重要なのは、鉄分の十分な補給と質の高い睡眠の確保です。
鉄分は“脳の栄養”でもある
鉄は、単に貧血予防のために必要なだけではありません。
神経伝達物質であるドパミンの合成に不可欠な要素であり、鉄が不足すると脳内のドパミン濃度が低下し、むずむず脚症候群のような感覚異常が生じやすくなります。
様々な研究によって、むずむず脚症候群患者の多くが体内の鉄レベル(特に脳脊髄液中の鉄)が低いことが明らかになっています。
鉄が多く含まれている代表的な食品
・レバーや赤身肉(ヘム鉄)
・ほうれん草や小松菜、大豆製品(非ヘム鉄)
非ヘム鉄は吸収率が低いため、ビタミンC(果物、ブロッコリーなど)と一緒に摂ると吸収率が上がります。

むずむず脚症候群を引き起こす要因は多岐にわたるため、鉄欠乏性貧血が原因の場合は内科的治療、パーキンソン病が原因の場合は脳神経内科というように対応が異なります。
いずれにしても自己判断はせず、医師に相談のうえ適切な治療を受けましょう。
むずむず脚症候群の治し方と日常の対処法
ここでは、医療機関に頼る前に実践できる具体的な対処法や、症状を和らげるために意識したい生活習慣、食事・栄養のポイントについて詳しく紹介します。
ストレッチ・マッサージ・入浴でリラックス
軽度のむずむず脚症候群であれば、日常的な対策で症状を緩和できます。
例えば、就寝前のストレッチやふくらはぎのマッサージ、40℃前後のぬるめの入浴などが効果的です。

睡眠リズムを整える生活習慣も重要
寝る時間・起きる時間を固定し、寝る前1時間はスマホやPCなどの刺激を避けるなど、睡眠環境の改善も大切です。
医療機関での治療や薬の選択肢も
重症の場合、医師の診断のもとでドパミン作動薬や抗てんかん薬が処方されることがあります。
ただし、薬には副作用もあるため、まずは生活習慣や栄養の見直しから始めるのが理想的でしょう。

まとめ|足がむずむずして寝れない夜に、今すぐできる対処を
むずむず脚症候群(RLS)は、放っておくと日常生活の質を大きく下げる睡眠障害です。
・チョコレートやカフェインなどの食品に注意する
・鉄分やマグネシウムなどの栄養をしっかり摂る
・ストレッチや入浴で身体を整える
ことが、改善への第一歩です。

それに加えて、睡眠の質をサポートするサプリメントの活用も効果的。
夜にぐっすり眠れる日々を取り戻すために、まずは自分に合った対処法を今日から始めてみませんか?