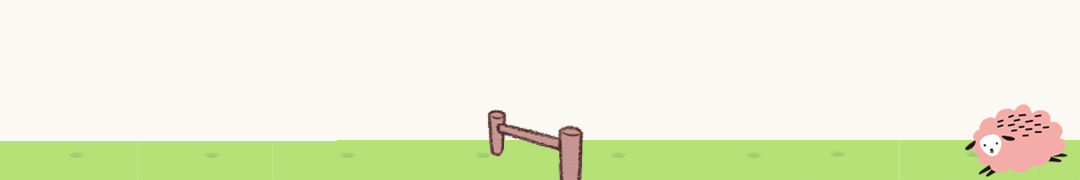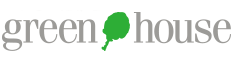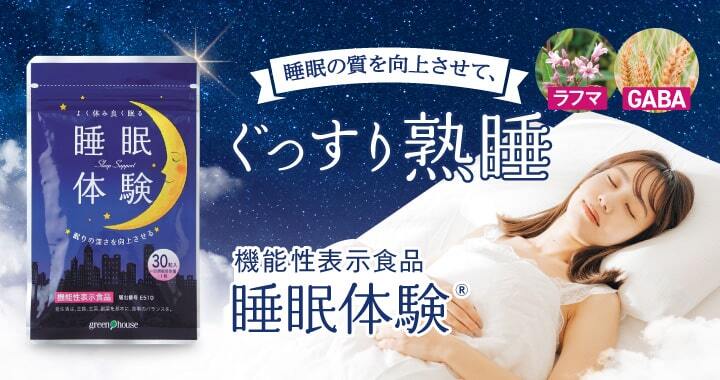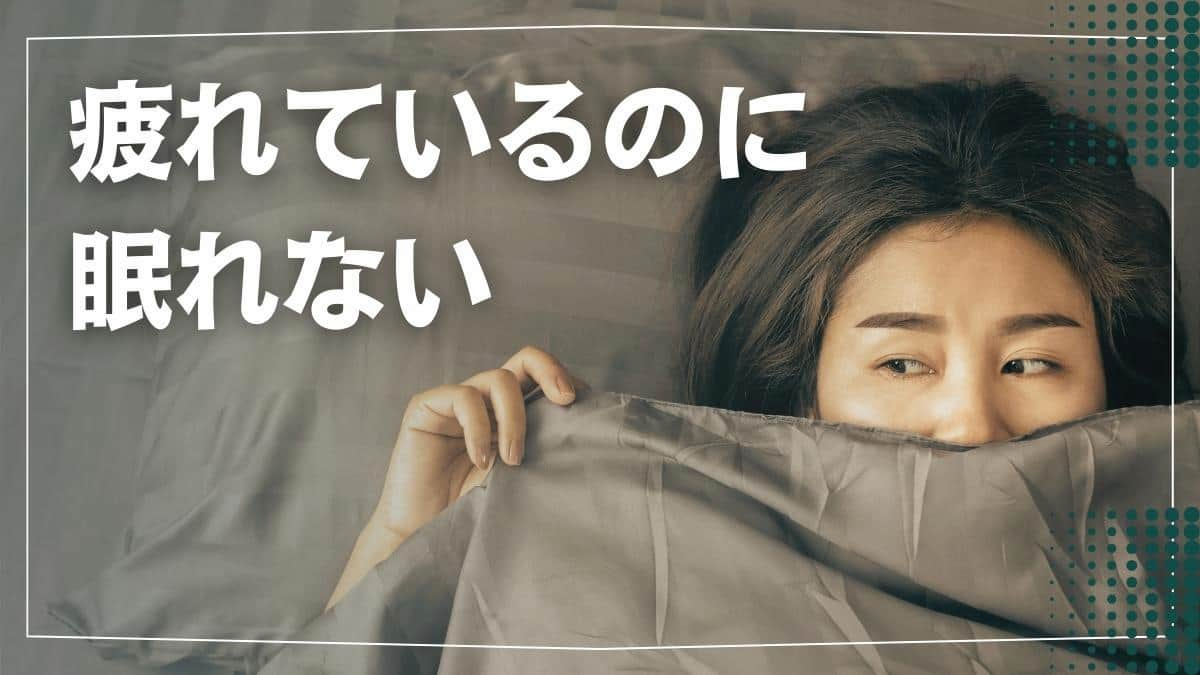寝付きが悪い、眠れない原因と対処法|入眠障害の治し方
最終更新日:2025.8.8

ベッドや布団に入ってもなかなか眠れない人や、寝つくまでに時間がかかる人は、入眠障害かもしれません。
入眠障害や中途覚醒は、不眠症の代表的な症状の1つであり、睡眠時間が短くなるだけでなく、睡眠の質が低下し、十分な休息感が得られにくくなることがあります。
今回は、眠れない原因や入眠障害の症状、寝つきを良くするための対処法などを詳しく解説します。

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
睡眠栄養指導士
小田 健史
健康食品業界で数々の商品開発や販促に12年以上携わる。
睡眠不足に悩まされ続けた自身の不眠体験から、一念発起して「睡眠栄養指導士」の資格を取得し、自らの知識と経験を基に機能性表示食品に登録された睡眠向上サプリ「睡眠体験」を開発。
現在、睡眠栄養指導士として多くの悩める方々へ睡眠の改善に関する情報を発信中!
<資格>
・一般社団法人 睡眠栄養指導士協会
睡眠栄養指導士® 中級
パーソナル睡眠アドバイザー®
・特定非営利活動法人 日本成人病予防協会
健康管理士 一般指導員
入眠障害とは
寝床に入っても目が冴えてなかなか寝付けない日が頻繁にある人は、入眠障害の可能性があります。 入眠障害は不眠症の症状のひとつで、特に多くみられる睡眠トラブルです。
入眠障害は、不眠症状の中でも特に多い睡眠トラブルです。
入眠障害の症状
入眠障害には国際的な診断基準があり、以下のような状態が続いている場合、入眠障害が疑われます。

- ベッドや布団など寝床に入ってから30分~1時間以上寝付けない日が週に3回以上ある
- ①の状態が少なくとも1カ月以上続いている
- 日中に強い眠気や集中力の低下、作業能率の低下がみられる
- 気分の不安定さや意欲の低下を感じることがある
入眠障害の影響
入眠障害が続くと、慢性的な睡眠不足になるだけでなく、睡眠が浅くなったり断片化することで、眠りの質が低下します。
その結果、昼間に強い眠気を感じて集中力が低下したり、気分が不安定になりイライラしやすくなることがあります。
入眠障害が与える悪影響
-
- 慢性疲労やだるさを感じやすくなる
- 集中力や記憶力の低下
- 肌荒れが起きやすくなることがある
- 太りやすくなるリスクが高まる
- 高血圧や糖尿病などメタボリックシンドロームのリスクが上昇する可能性がある
入眠障害の原因は?寝付きが悪くなる理由とは
入眠障害は、複数の原因が複雑に関わり合って引き起こされることが多い不眠症状です。
以下のような要因が関与することが多く、当てはまるものがないか振り返ってみると役立ちます。

- ストレスや過度の緊張
- 不規則な生活(昼夜逆転、就寝時刻のばらつきなど)
- 女性ホルモンの影響(更年期、月経前、妊娠中など)
- 身体的疾患(痛み、かゆみなど)や精神的疾患(うつ病、不安障害など)の影響
- カフェインやアルコール、薬の影響
- 眠れないことに対する焦りや不安
それぞれの内容について詳しく解説いたします。
ストレスや過度の緊張
ストレスは入眠障害の大きな原因の1つです。ストレスによって交感神経が活性化し、心身が緊張状態になると、眠りにつきにくくなります。
体内時計の乱れが「メラトニン」の分泌タイミングに影響
また、ストレスの影響で体内時計のリズムが乱れ、睡眠を調整する「メラトニン」の分泌タイミングに影響を与えることがあります。
日中、太陽光を浴びることで脳内のセロトニンが活性化され、その後夜になるとセロトニンをもとにメラトニンが松果体で合成されます。メラトニンが十分に分泌されることで、入眠がスムーズになり、睡眠の質が保たれるのです。

しかし、ストレスによってセロトニンの神経系の機能低下や神経伝達の異常が起こると、神経活動の調節機能が低下して入眠障害を引き起こすこともあります。
ストレスで自律神経が乱れて眠れなくなる
セロトニンは自律神経系の調節に関与しています。
自律神経とは
-
- 交感神経
日中の活動的な時間帯に働く。血圧を上昇させたり、心拍数を上げたりして身体を興奮状態にする - 副交感神経
リラックスした時や休息中に優位になる。血圧を下降させたり、心拍数を下げたりする
- 交感神経
ストレスによりセロトニンの分泌量が減ると、自律神経がバランスを崩しやすくなります。
すると、就寝時間になっても交感神経が昂った興奮・緊張状態が続き、眠れなくなるのです。
「あぁ…今日も眠れない…」寝つきが悪い人が急増中!セロトニンを増やして今夜はぐっすり >> 解決法がこちら
不規則な生活
不規則な生活リズムは、入眠障害の大きな要因です。
起床・就寝時間や食事のタイミングが毎日異なると、体内時計(概日リズム)が乱れやすくなります。
その結果、睡眠を促すホルモンの分泌や自律神経のリズムが崩れ、夜になってもなかなか寝付けない状態になることがあります。

女性ホルモンの影響
女性の入眠障害の一因として、女性ホルモンの変動、とくに月経前に増えるプロゲステロン(黄体ホルモン)の影響が挙げられます。
プロゲステロンによる体温上昇
生理前に分泌量が増える女性ホルモンの1つ「プロゲステロン(黄体ホルモン)」には、体温を上昇させる作用があります。
月経前は深部体温が通常より高めに保たれるため、深部体温の低下が不十分になり、寝つきが悪くなることがあります。


筑波大学教授 櫻井 武
プロゲステロンによる影響の程度や感じ方には個人差があります。
体温上昇がすべての女性に強い入眠障害をもたらすわけではないので、自身の状態に気を配りましょう。
更年期による女性ホルモンの分泌量低下
更年期になると、女性ホルモン(特にエストロゲン)の分泌が減少し、自律神経のバランスが乱れやすくなります。
その結果、夜間に交感神経が高ぶりやすく、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりすることがあります。
また、ホットフラッシュや不安感、動悸といった更年期障害の症状も、入眠障害の大きな要因となります。

病気の影響
病気によって寝付きが悪くなることも珍しいことではありません。入眠障害の原因になりやすいのが、以下の疾患です。

レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)
「レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)」は中高年女性で比較的多く、特に妊娠中や鉄欠乏のある人でリスクが高くなります。発症原因の1つとして、鉄分不足が挙げられます。

筑波大学教授 櫻井 武
レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)」の発症原因は、鉄分不足以外にも遺伝的要因や、脳内でドパミンという神経伝達物質を介して情報伝達する神経経路『ドパミン系』の異常も関与します。
レストレスレッグス症候群になると、夕方から夜にかけて脚にムズムズとした感覚や虫が這うような感覚が出現し、「脚を動かしたい」という欲求に襲われて眠れなくなります。
アレルギー性鼻炎
アレルギー性鼻炎は夜間から早朝にかけて症状が悪化することが多いと言われています。
アレルギー性鼻炎患者を対象に行われた睡眠調査では患者の63%が睡眠の質の悪さを感じ、特に入眠困難が示唆される結果が明らかになりました(※1)。
糖尿病
糖尿病の人は、睡眠障害を引き起こしやすいことが指摘されています。
ある調査では、糖尿病外来を受診した人のうち約40%に睡眠障害があり、中でも入眠困難を訴える患者が多いことが報告されました(※2)。
うつ病
うつ病と睡眠障害には深い関連性があり、うつ病の病相期では入眠障害が73.3%、熟眠障害が89.9%、全体として94.1%以上の患者に何らかの睡眠障害が認められたという調査結果があります(※3)。
ほかにも不安障害や心的外傷後ストレス障害(PTSD)など、さまざまな精神的疾患が入眠を妨げる要因となります。
※1:本間あや. "アレルギーと睡眠を制御する体内時計." 日本鼻科学会会誌 60.1 (2021): 101-102.
※2:清水夏恵, 村松芳幸, and 成田一衛. "糖尿病患者の睡眠障害について (特集 内分泌・代謝疾患の心身医療)." 心身医学 53.1 (2013): 29-35.
※3:精神疾患における睡眠・覚醒リズムの評価とその意義/精神経誌(2010)112巻9号
カフェインやアルコール、薬の影響
コーヒーやお茶、チョコレートなどに含まれるカフェインの覚醒作用は効果がなくなるまでに時間がかかるため、夕方以降に摂取すると就寝時間になっても眠れなくなることがあります。
また、寝付きを良くするために「眠る前の一杯」を習慣にしている人もいるかもしれません。
寝る前のアルコールは一時的に入眠を促しますが、その後アルコールが分解されて生じるアセトアルデヒドという物質の覚醒作用によって眠りが浅くなるほか、アルコール自体の作用によっても睡眠の質が低下します。
寝る前の飲酒が習慣化するほど、酒量は増加。眠るためにより多くのお酒が必要となり、やがてアルコール依存症を引き起こす可能性が高くなります。
その他に、ステロイド系や中枢神経に作用するものなど、服用している薬が入眠障害の原因となるケースもあります。
眠れないことに対する焦りや不安
眠れないことに不安や焦りを感じて、寝るためにとる対処行動が余計に入眠障害を悪化させる可能性が高いことが、大学生を対象に実施された調査によって報告されています(※)。
※:入眠障害と入眠時の対処行動の関連/行動医学研究 Vol.17,No.1
寝つきで悩む人必見!セロトニンを増やし、眠りの質を改善する方法 >> 詳しく見る
寝付きを良くする方法は?寝付きが悪い時の対処法
次にご紹介するのは、入眠障害を改善するための対処法です。
- 朝起きたらすぐに太陽の光を浴びる
- 一定のリズムで体を動かす
- セロトニンの分泌量を増やす食品を食べる
- 睡眠の質を高めるサプリメントを活用する
- 寝る前に温かいドリンクを飲んで体温を上げる
- 午後3時以降や長時間の昼寝はしない
- 寝室の温度や湿度環境を整える
- 眠りにつきやすくなるルーティンを取り入れる
- 寝床へ入るのは眠気を感じた時だけにする
それぞれの対処法について、以下で具体的に解説いたします。簡単に実践できるものばかりですので、毎日の暮らしに取り入れやすい方法を試してみませんか。

朝起きたらすぐに太陽の光を浴びる
起床後に日光を浴びることで、「体内時計のリセット」を促せます。
朝起きたら、まずカーテンを開けて朝日を浴びるようにしましょう。
この習慣を毎日続けることで体内時計が整い、入眠障害の改善効果が期待できます。
一定のリズムで体を動かす
研究によって、一定のリズムで体を動かすことがセロトニンの分泌量増加につながることが分かっています(※)。
激しい運動である必要はなく、ウォーキングやジョギング、踏み台昇降などの軽い運動でも効果的です。

※:佐野新一, et al. "踏み台昇降運動によるセロトニン神経系の賦活." 北陸大学紀要 26 (2002): 39-48.
セロトニンの分泌量を増やす食品を食べる
セロトニンの原料となる「トリプトファン」と、トリプトファンからセロトニンを生成する際に必要な「ビタミンB6」を含む食品を摂ることで、入眠障害の改善効果が期待できます。
トリプトファンを多く含む食品
-
- 牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品
- 納豆、豆腐、豆乳、味噌、ピーナッツなどの豆製品
- マグロ、カツオなどの赤身魚
- バナナ、キウイ、卵、ごま

ビタミンB6を多く含む食品
-
- 豚ヒレ、豚ロース、牛ランプ、鶏肉などの赤身肉、レバーなどの脂身の少ない肉類
- にんにく、玄米、抹茶

GABA
ストレスを軽減する働きがあることで注目されているGABA。
GABAは副交感神経を活発にしてリラクゼーション効果が期待できること(※1)や、入眠までの時間を短縮して深い睡眠の時間を増やす効果、また起きた際の気分の良さを改善する(※2)可能性があることが報告されています。
※1:藤林真美, 神谷智康, 高垣欣也, 森谷敏夫 GABA経口摂取による自律神経活動の活性化 日本栄養・食糧学会誌 61 (3), 129-133, 2008
GABAを多く含む食品
-
- トマト、ナス、納豆など


筑波大学教授 櫻井 武
ただし、食事からの摂取でトリプトファンやGABAなどの栄養素が与える影響には限りがありますので、バランスのいい食事を重視しましょう。
睡眠の質を高めるサプリメントを活用する
毎日の食事のみでセロトニンを増やす成分やGABAなどを十分に摂取することが難しい場合は、睡眠サプリメントで補う方法もあります。
睡眠の質を高めるために効果的おすすめの成分が、天然ハーブの一種である「ラフマ」です。
ラフマの葉っぱから抽出したラフマ由来ヒペロシド、イソクエルシトリンは、セロトニンの体内での減少を抑えつつ増加させることで、眠りの深さ、睡眠の質を向上させることが認められています(※)。
※:寺尾純二, メンタルヘルスを支える栄養科学 - 食品成分の抗うつ様活性評価 -, 四国医誌, 66, 123-126 (2010)

筑波大学教授 櫻井 武
まずはバランスのいい食事や規則正しい生活習慣を心がけましょう。サプリメントの活用は補助的手段としての選択肢の1つです。
寝る前に温かいドリンクを飲んで体温を上げる
温かい飲み物を摂取することでも、体温を上昇させた後に体の中心部が冷えていく過程で眠気を感じやすくなります。
ポイントは、カフェインを含まない飲み物をゆっくりと少しずつ飲むこと。ハチミツを加えたホットミルクや、リラックス効果が高いカモミールのハーブティーがおすすめです。
午後3時以降や長時間の昼寝はしない
夜に眠れないと、日中についウトウトしてしまうことがありますよね。移動中の電車の中や会議中など、寝落ちトラップは至る所にあります。

小田
私が習慣にしているのは、15分間の昼寝です。
昼食後、デスクに顔を伏せて寝ていますが、目覚めた時には頭がスッキリします。午後の仕事効率も上昇するので、一押しの習慣です。
とは言え、長時間の昼寝は夜の睡眠時間に影響を与えて入眠障害を引き起こす原因になります。
昼寝の効果を最大限に活かすためには、正午~午後3時の間で10分~20分程度とるようにしましょう。
「セロトニンを増やすラフマ」&「ストレスを軽減させるGABA」【日本初】W効果の睡眠サプリで寝つき改善 >> 詳しく見る

寝室の温度や湿度環境を整える
眠りにつく環境も、寝付きの良さと睡眠の質に関係しています。
快適な寝室の温度は、夏は25℃~26℃、冬から春先が16℃~19℃(※1)、結果として寝床内での体周辺の温度は33℃になっていれば睡眠の質は下がらない(※2)とされています。
また、湿度は年間を通じて50%~60%が最適となります(※3)。

エアコンや加湿器、寝具を調整して、快適な環境を整えましょう。
※1,3:宮崎, 総一郎, and 佐藤. "医療・看護・介護のための睡眠検定ハンドブック."
眠りにつきやすくなるルーティンを取り入れる
寝付きを良くするためのルーテインをご紹介します。深部体温を下げることと、副交感神経を優位にするのがポイントです。
就寝の1~2時間前に入浴する
人は身体の深部体温が下がると眠くなり、入眠しやすくなる性質を持っています。
お風呂に浸かることで一度上がった深部体温は、その後に元に戻そうとする働きにより下がります。ただしあまり熱いお湯につかると交感神経を刺激して逆効果となりますので、寝る1~2時間前に約40℃の少しぬるめのお風呂につかるのが重要です。
お風呂にはリラックスして副交感神経を優位にする効果もあるので、寝付きの悪さに悩んでいる人はシャワーのみではなくできるだけ湯船に浸かるようにしましょう。
ストレッチやヨガを寝る前の日課にする
寝る前に軽いストレッチやヨガのポーズを行うと、身体の緊張がほぐれて副交感神経が優位になります。
特にヨガは深い呼吸を意識して行うため、リラックス効果が抜群です。

小田
最初は「面倒だな」と思うかもしれませんが、まずは3日間続けてみてください。
効果を実感できると、毎日やることが当たり前のように感じられてきますよ。
寝床へ入るのは眠気を感じた時だけにする
就寝時刻になったからと言って眠くないのにベッドへ入り、そのまま眠れない時間を過ごすことが入眠障害を悪化させる要因となります。
寝床で眠れない時間が長くなると、寝室や寝具などが「眠れない場所」として意識に刻み込まれてしまいます。
その結果、寝室や寝具に入ることで余計に眠れなくなる可能性が高くなるのです。
もしも寝床に入って20分以内に眠れない場合は、一度寝床から離れましょう。
入眠障害を解消して質が高い睡眠をとろう
今回は、なかなか寝つけない「入眠障害」の症状や原因、改善方法をご紹介しました。
入眠障害による寝不足や睡眠の質の低下は、居眠り運転や仕事中の重大事故などを引き起こす危険性があるだけでなく、心疾患など将来的な健康リスクを上昇させます。
「最近、スムーズに寝つけない」という人は、生活習慣や食生活を見直してみませんか。
それでも症状が改善しない時は、医師や専門機関に一度相談することをおすすめします。
入眠障害 Q&A
入眠障害でお悩みの方向けに、よくあるご質問と回答をまとめました。入眠障害の治し方の参考にしてみてください。
- 1.入眠障害の原因は?
- 比較的自覚症状がある、病気などの身体的原因やカフェイン・アルコールなどの一時的な原因の他に、自律神経の乱れや、生活習慣、ストレス等で寝付きが悪くなります。
- 2.入眠障害への対策を教えてください。
- 起きたら太陽の光を浴びる、適度な運動を行うといった、体内時計を整えたりセロトニンの分泌を促したりする行動を心がけることが大切です。
そして寝る前には照明やテレビ・スマホの強い光を浴びないようにして、リラックスして副交感神経が優位になるような習慣も取り入れましょう。 - 3.入眠障害が続く場合はどうすればいいですか?
- 生活パターンの見直しのみで入眠障害の改善が難しい場合は、トリプトファンやGABAといった睡眠の質を高める成分を摂取するようにしましょう。
自然由来の栄養素が主成分のセロトニンの分泌を増やす睡眠サプリメントは、睡眠薬のような依存性もないため安心して活用することができます。

筑波大学大学院医学研究科博士課程卒業(1993年)。
卒業後、筑波大学基礎医学系に入局。助教授、准教授を経て、2008年から金沢大学医薬保健学総合研究科に教授として着任。2016年から現在の筑波大学医学医療系の教授を務める。
<主な受賞歴>
・第11回つくば奨励賞
・第14回安藤百福賞大賞
・第65回中日文化賞
・平成25年度 文部科学省 科学技術賞
・第2回塩野賞
・第32回つくば賞
<主な論文>
・Emi Hasegawa, Ai Miyasaka, Katsuyasu Sakurai, Yoan Cherasse, Yulong Li, Takeshi Sakurai. Rapid eye movement sleep is initiated by basolateral amygdala dopamine signaling in mice. Science. 2022 Mar 4;375(6584):994-1000.2022.
・Takahashi TM, Sunagawa GA, Soya S, Abe M, Sakurai K, Ishikawa K, Yanagisawa M, Hama H, Hasegawa E, Miyawaki A, Sakimura K, Takahashi M, Sakurai T. A discrete neuronal circuit induces a hibernation-like state in rodents. Nature. 2020 Jul;583(7814):109-114.2020.