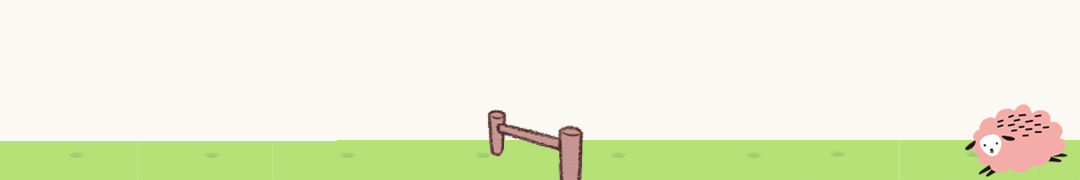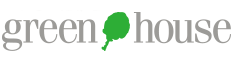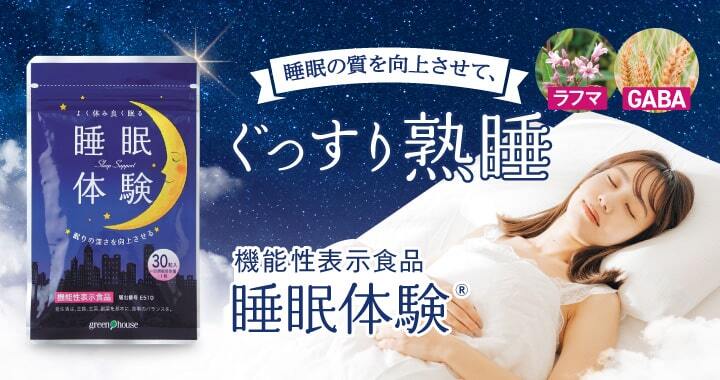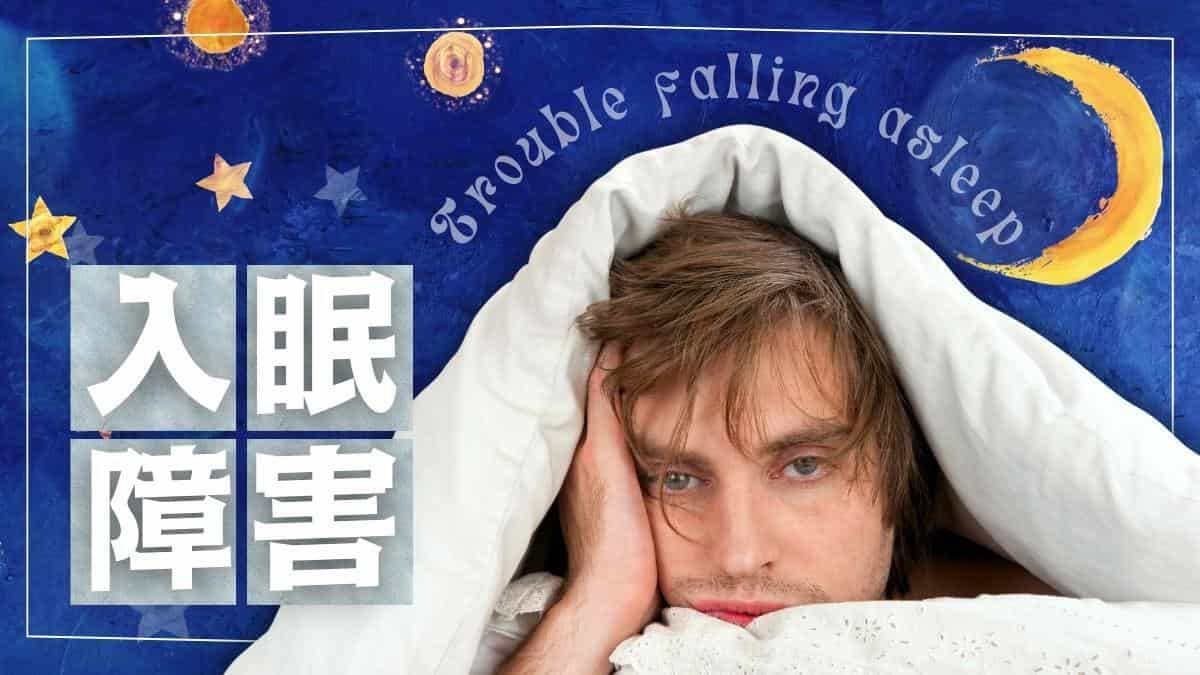お酒で眠くなる理由と睡眠への影響 | 目が冴える原因も解説
最終更新日:2025.05.21
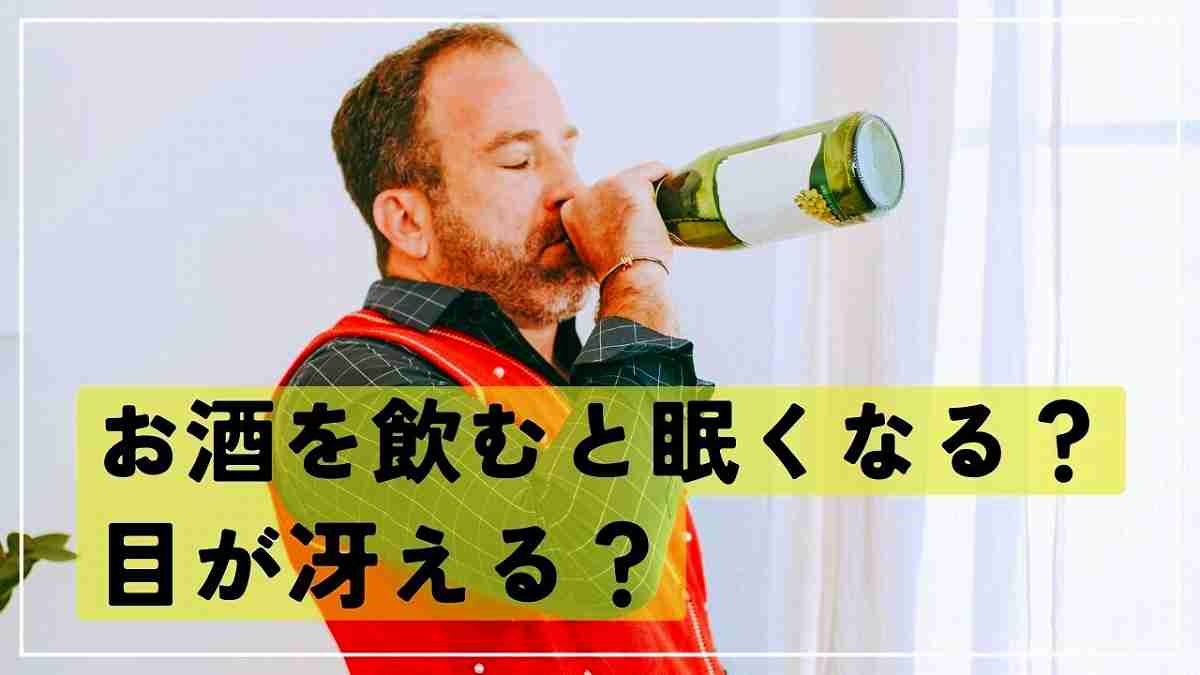
寝る前にお酒を飲むと「すぐに眠くなる」という人もいれば、「逆に目が冴えて眠れない」と感じる人もいます。
なぜ同じお酒でも、眠りに違いが出るのでしょうか?
本記事では、寝酒が睡眠にどのような影響を与えるのか、そのメカニズムと体質による違いをわかりやすく解説します。
お酒と睡眠の関係を正しく知り、毎晩の眠りを見直したい方は、ぜひ最後までお読みください。

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
睡眠栄養指導士
小田 健史
健康食品業界で数々の商品開発や販促に12年以上携わる。
睡眠不足に悩まされ続けた自身の不眠体験から、一念発起して「睡眠栄養指導士」の資格を取得し、自らの知識と経験を基に機能性表示食品に登録された睡眠向上サプリ「睡眠体験」を開発。
現在、睡眠栄養指導士として多くの悩める方々へ睡眠の改善に関する情報を発信中!
<資格>
・一般社団法人 睡眠栄養指導士協会
睡眠栄養指導士® 中級
パーソナル睡眠アドバイザー®
・特定非営利活動法人 日本成人病予防協会
健康管理士 一般指導員
目次
寝酒で眠気を感じる理由 | 脳の仕組みを分かりやすく解説
「寝る前にお酒を飲むと、すぐ眠くなるから、寝酒は悪くない」。
そう思っていませんか?
確かに、アルコールには一時的に眠気を引き起こす作用があります。
しかしその眠気は、私たちが本来持っている自然な眠りとはまったく違うもの。
その正体を知ることで、睡眠の質を守る第一歩になります。

眠気とGABA(ギャバ)の関係
アルコールがもたらす「眠気」は、脳の神経伝達物質「GABA(ギャバ)」の働きを強化することが主な理由です。
GABAには副交感神経の働きを活性化させてリラックス感を高めたり、ストレスを緩和したりする作用があるとされています(※)。
実は“質の悪い眠り”を招くリスクも
しかし、この眠気はあくまでもアルコールによる薬理作用の一種で、自然に訪れる眠気とは異なります。
つまり、“寝つきやすくなる”だけで、“熟睡できる”とは限らないのです。
この差を見落とすと、睡眠の質の低下に気づかないまま寝酒を続けてしまうリスクがあります。

睡眠科学の研究では、アルコールは入眠を助ける反面、睡眠の質を著しく低下させることが明らかになっています。
特に深い眠り(ノンレム睡眠)の時間が減り、睡眠が浅くなりやすい傾向があることが指摘されているのです。
厚生労働省が発表した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」でも、寝酒は一時的には寝つきを良くするものの、睡眠後半の眠りの質を悪化させるため、寝る前の飲酒を控えるように警鐘を鳴らしています。
※藤林真美, et al. "GABA 経口摂取による自律神経活動の活性化." 日本栄養・食糧学会誌 61.3 (2008): 129-133.
「お酒で目が冴える人」がいるのはなぜ?体質・神経メカニズムの違い
「寝酒をしてもなぜか眠れない」「逆に目が冴えてしまう」という悩みを持つ人も少なくありません。
これは単なる気のせいではなく、個人の体質や脳・神経の働き方に深く関係しています。
なぜお酒を飲んでも眠れないのか、その理由を解説します。
アセトアルデヒドの覚醒作用
まず注目したいのが、アルコールの代謝に関係する酵素の遺伝的な個人差です。
アルコールは、アルコール脱水素酵素1B(ADH1B)でアセトアルデヒドになり、アルデヒド脱水素酵素2(ALDH2)で酢酸に代謝されます(※)。
日本人のおよそ40%は、アルコールを分解する酵素「ALDH2」の働きが弱いとされており、アセトアルデヒドが体内に蓄積しやすい傾向があります。
このアセトアルデヒドには覚醒作用があるため、眠気どころか神経を刺激して“目が冴える”状態を招くケースが少なくありません。
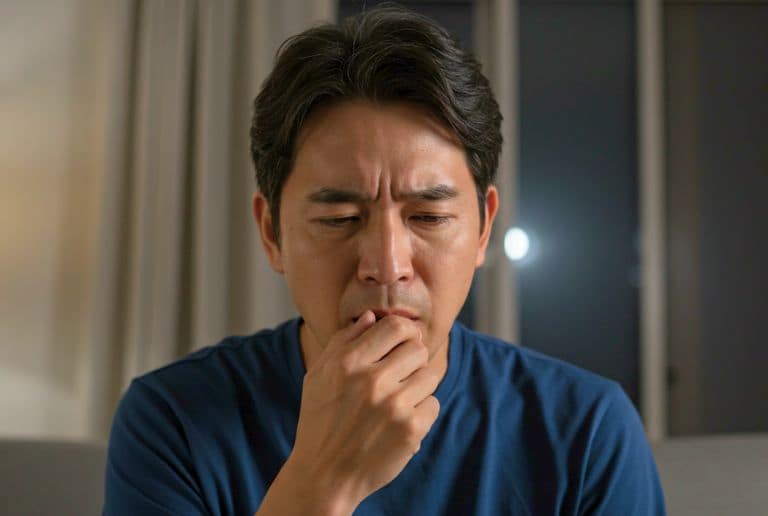
自律神経の乱れ
アルコールは、自律神経にも影響します。
自律神経は心拍数や呼吸、体温調節など睡眠の質に大きく関わるシステムで、アルコールの影響で交感神経が過剰に刺激されると、興奮状態が続き「目が冴える」感覚を生むことがあります。
このように、体質や自律神経の状態によって、同じ寝酒でも眠気の感じ方や睡眠の質は大きく異なるため、自分の体に合った睡眠習慣を見つけることが重要です。

※横山顕. "アルコール代謝と健康障害." 産業精神保健 32.2 (2024): 171-177.
寝酒が睡眠の質に与える5つの悪影響 | 具体的な症状も紹介
寝酒を習慣にしていると、「眠気はあるけど翌朝疲れが取れない」「夜中に何度も目が覚める」といった悩みが起きやすくなります。
これは、お酒が睡眠の質に悪影響を及ぼしているサインかもしれません。
具体的にどのようなリスクがあるのかを、5つのポイントに分けて解説します。
① 深い眠り(ノンレム睡眠)が減少
深い眠りは身体の疲労回復や免疫機能向上に不可欠です。
アルコールはこのノンレム睡眠の割合を減らし、浅い眠りを増やすため、睡眠の回復力が低下します。
② 中途覚醒の増加
アルコールの利尿作用によって夜中にトイレに起きる回数が増え、睡眠が断続的に。
さらに体内でのアルコール分解に伴う覚醒作用も加わり、途中で目が覚めやすくなります。

③ レム睡眠の乱れ
レム睡眠は記憶の整理や精神の安定に関わります。
アルコールによってこのサイクルが乱れると、翌日の集中力や気分が不安定になる恐れがあります。
④ 睡眠時無呼吸症候群の悪化
アルコールは喉の筋肉を弛緩させ、気道が狭くなるため、睡眠時無呼吸症候群の症状を悪化させるリスクがあります。
無呼吸による酸素不足は心身に大きな負担となります。
⑤ 依存性と耐性形成
寝酒の習慣が続くと、同じ量では眠気が感じにくくなり、飲酒量が増加。
依存症のリスクや睡眠障害の慢性化を招きます。

寝酒の代わりに、無理なく続けられる快眠サポートを始めてみませんか?
▶︎ 快眠のためのサポート方法を見る
まとめ | お酒と睡眠の関係を正しく理解し、快眠習慣を手に入れよう
寝酒は確かに一時的に眠気をもたらすものの、長期的には睡眠の質を大きく下げ、心身の健康にも悪影響を及ぼします。
体質や神経の個人差から「お酒を飲んでも眠れない」「逆に目が冴える」と感じる人もいるため、一律の対処法はありません。

睡眠の質を高めるには、生活リズムの改善や環境づくり、精神的リラックス法を積極的に取り入れることが不可欠です。
どうしても寝酒をやめられない場合は、自然な眠りを助ける生活習慣や睡眠の質を高める成分が配合されたサプリメントを活用するのも、効率的な方法でしょう。
寝酒に頼らず、自然な眠りを手に入れる方法をお探しの方は、
▶︎ 快眠サポートの詳細はこちら
よくある質問 | お酒と睡眠に関するQ&A
寝酒の代わりにサプリを取り入れることで、より質の高い睡眠を目指す方が増えています。 詳しくは下記のリンクから、成分や選び方のポイントをご確認ください。
睡眠サポートサプリメントの詳細はこちら