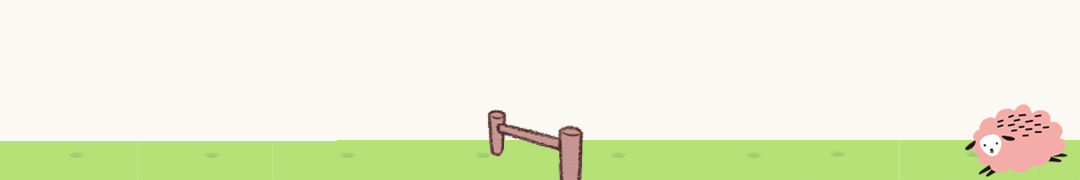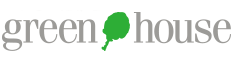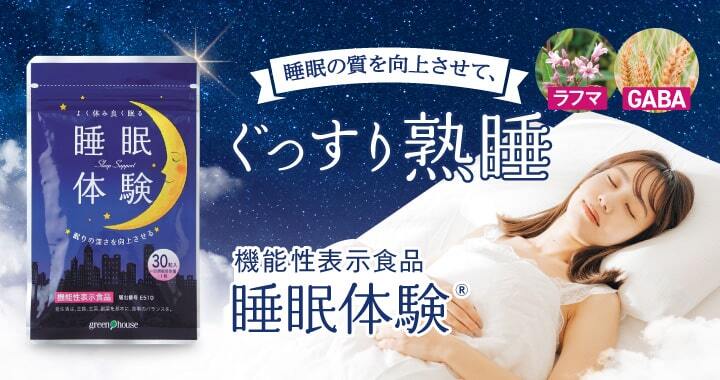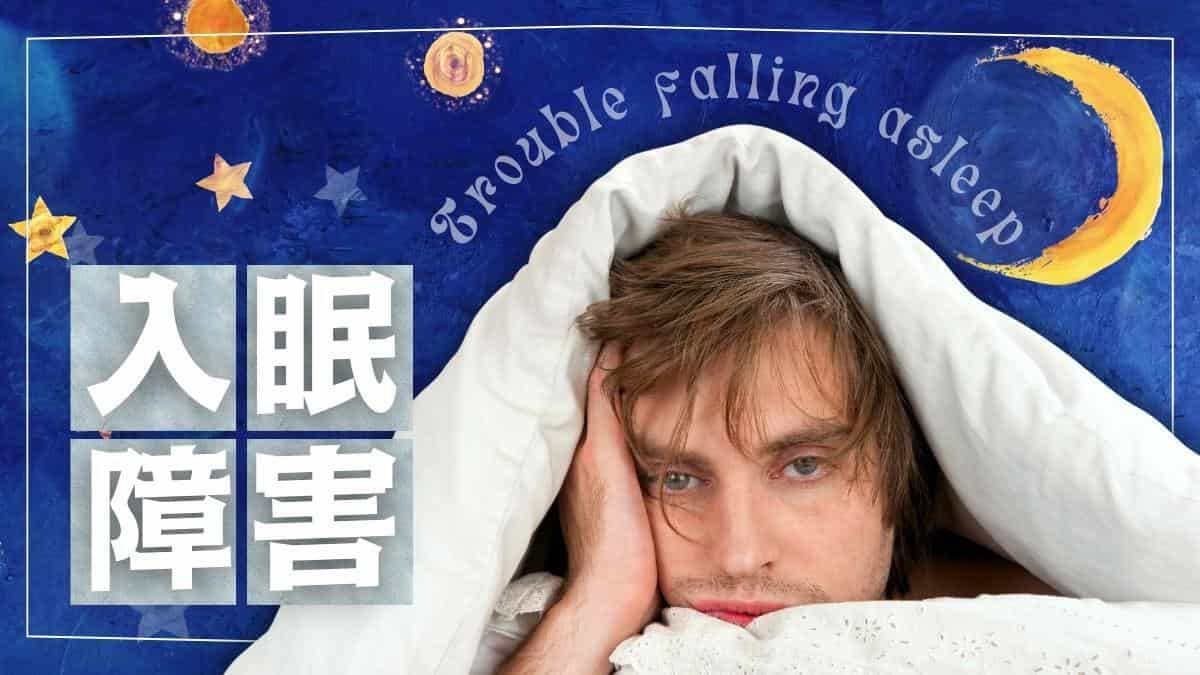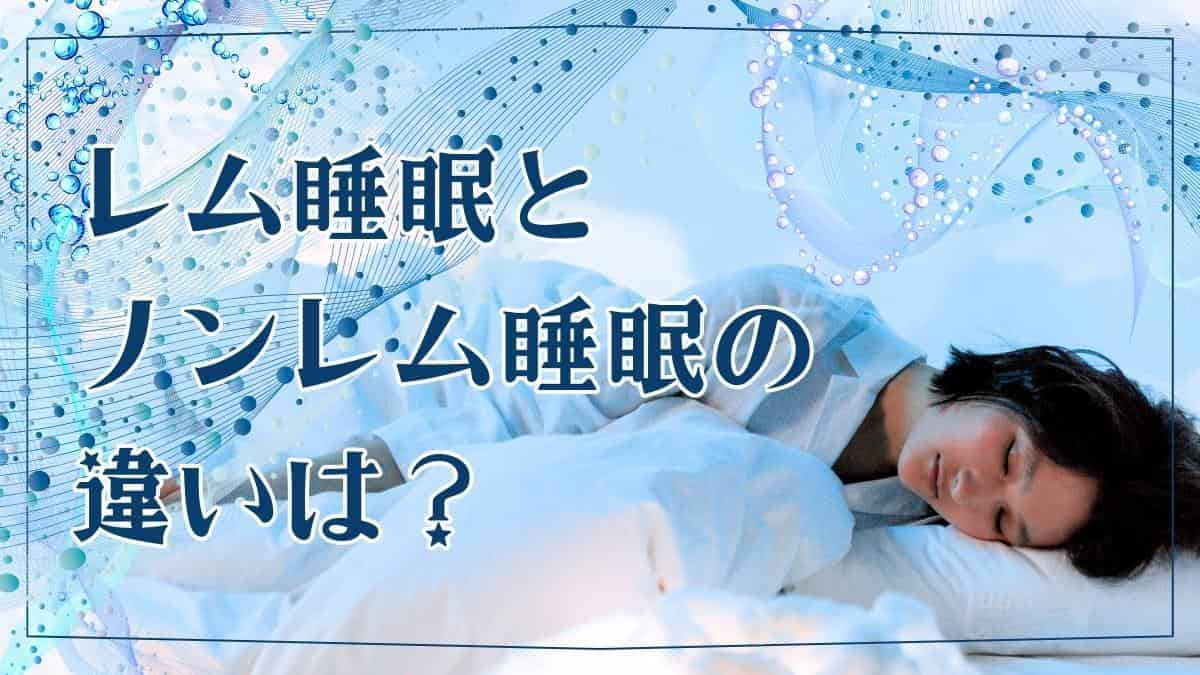眠りが浅い原因は?睡眠を改善して深い眠りにつく方法
最終更新日:2024.12.26

「すぐに起きる」「夢ばかり見る」「長めに寝たのに、仕事中に強い眠気を感じる」。
毎日の睡眠に満足できていない人は、睡眠時間の長さだけではなく眠りが浅いことが原因かもしれません。
今回は睡眠アドバイザーとしての知識を交えながら、眠りが浅い理由と、深い眠りにつく方法として簡単に実践できるライフスタイルの改善策をご紹介したいと思います。
睡眠の質に満足できていない方は、ぜひ参考にしてくださいね。

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
睡眠栄養指導士
小田 健史
健康食品業界で数々の商品開発や販促に12年以上携わる。
睡眠不足に悩まされ続けた自身の不眠体験から、一念発起して「睡眠栄養指導士」の資格を取得し、自らの知識と経験を基に機能性表示食品に登録された睡眠向上サプリ「睡眠体験」を開発。
現在、睡眠栄養指導士として多くの悩める方々へ睡眠の改善に関する情報を発信中!
<資格>
・一般社団法人 睡眠栄養指導士協会
睡眠栄養指導士® 中級
パーソナル睡眠アドバイザー®
・特定非営利活動法人 日本成人病予防協会
健康管理士 一般指導員
目次
眠りが「浅い」「深い」ってどんな状態のこと?
よく眠れたことを「深く眠れた」と表現しますが、なぜ眠りは「浅い」「深い」で言い表されるのでしょうか?
その理由として、「レム睡眠」「ノンレム睡眠」と呼ばれる90分ごとのサイクルで繰り返す眠りの状態が挙げられます。
レム睡眠
よく「浅い眠り」と表現されるのが「レム睡眠」です。
「レム」とは、英語で「眼球が素早く動く」(Rapid Eye Movement)という意味を表す言葉の頭文字からつけられた名前であり、レム睡眠時には眼球が活発に動くことが由来となっています。
レム睡眠時は、体はリラックスして疲労を回復していますが、脳は働いて記憶の整理や定着を行っています。
体は休んでいても脳は覚醒しているため、いわゆる「金縛り」を体験するのはレム睡眠時である場合がほとんどです。

ノンレム睡眠
脳を休ませて深い睡眠状態になるのが「ノンレム睡眠」です。
ノンレム睡眠時には成長ホルモンなどが分泌され、体内の機能を整えます。
「夢を見るのはレム睡眠の時」と長年言われてきましたが、近年ではノンレム睡眠の時にも夢を見る事が明らかになっています。

睡眠中は、このレム睡眠とノンレム睡眠が交互に訪れます。
そうして目覚めの時間が近付くにつれて、深いノンレム睡眠から浅いノンレム睡眠の時間が増えて覚醒に至るのです。
ノンレム睡眠中に見た夢は記憶に残りにくいのに対して、レム睡眠中に見た夢は覚えていることが多いとされています。
眠りが浅い時に「夢ばかり見る」と感じやすいのは、このような理由があるからなのです。
眠りの質を左右する「眠りのゴールデンタイム」

三島和夫. 眠りのメカニズム. e-ヘルスネット
「図4: 夜間睡眠パターン 厚生労働省 (2021)」を基に作成
ノンレム睡眠は、眠りの深さによってさらに分類されます。
もっとも深い睡眠状態は「N3」や「ステージ4」、「徐波睡眠」と呼ばれ、入眠してから最初の約90分間に訪れます。
この90分間は「眠りのゴールデンタイム」とも呼ばれ、この時に深く眠れると質が高い睡眠を得られます。
しかし、寝つきが悪いなどの理由で深いノンレム睡眠に入れなかった場合は、疲労回復が実感できるような質の高い睡眠を得られないでしょう。
眠りが浅い人の特徴!睡眠が浅いとどんな影響がある?
浅い眠りや睡眠不足が続いている人には、以下のような影響があらわれます。
眠りが浅い人の特徴
-
- ・夜中に目が覚めやすい
- ・日中に眠気を感じる
- ・日中の集中力が低下している
- ・記憶力が低下している
- ・イライラしたり、怒りっぽい
- ・寝ても疲れが取れない
眠りが浅いことによる健康への悪影響
浅い眠りや睡眠不足が続いて深く眠れないことが慢性化している時、体の内部では健康を損なう状態への変化がじわじわと起きています。
睡眠中は成長ホルモンなどが分泌され、免疫力アップや傷ついた箇所を修復。
また、疲労回復やストレス緩和、その日あった出来事や吸収した知識などを整理し、脳に固定化しています。
しかし、深く眠れない場合、そういった睡眠による疲労回復やリフレッシュ、記憶の整理・固定などが行われません。
そのため、免疫力が落ちて感染症にかかりやすくなったり、慢性的な疲労感を覚えたり、記憶力・集中力が低下するなどの悪影響が表れるのです。
更年期の女性は眠りが浅い⁉更年期症状と浅い眠りの関係

40代半ばから50代前半の女性は、更年期の影響で睡眠障害になりやすいことが分かっています。
厚生労働省の健康情報サイト「e-ヘルスネット」によると、更年期を迎えた女性の約半数が不眠や就寝に関する悩みを抱えているとされています。
更年期の女性に不眠症状が起こる原因として挙げられるのが、女性ホルモンの分泌量低下です。
女性ホルモンの「エストロゲン」には睡眠を調整する働きがあります。
しかし、閉経にともないエストロゲンの分泌量が減ると眠りが浅くなったり、寝つきが悪くなったりといった睡眠障害を引き起こすのです。
眠りが浅い原因は?深く眠れないのはなぜ?

眠りが浅くなる原因として、自律神経やホルモンの影響が挙げられます。
自律神経と浅い眠りの関係
自律神経には、交感神経と副交感神経の2種類があります。
交感神経
日中に優位になるのが交感神経です。
心拍数を増やしたり、血圧を上昇させたりと身体の動きを活性化させます。
副交感神経
夕方以降に優位になるのが副交感神経です。
心拍数を減少させたり、血圧を低下させたりして身体をリラックスモードにして眠るための準備を整えます。
私たちの体は、この2つの自律神経が自動的にバランス良く切り替わることで、健康に保たれています。
しかし、自律神経はストレスや生活環境によって乱れやすく、バランスを崩すことが少なくありません。
すると、夜になっても交感神経が昂ったままで、興奮・緊張した状態に。
スムーズな入眠が妨げられるだけでなく、睡眠サイクルが乱れて最初の深いノンレム睡眠まで到達できなくなります。
そのため、その夜の眠り全体が浅くなって睡眠の質が悪くなるのです。
幸せホルモン「セロトニン」と浅い眠りの関係

眠りが浅くなる原因には、“幸せホルモン”と呼ばれる神経伝達物質「セロトニン」の分泌量が深く関わっています。
セロトニンの働き
セロトニンは日中に生成され、メンタルの安定やストレス緩和、頭の回転を良くして直観力を高めるなどの作用がある神経伝達物質です。
日中に分泌されたセロトニンは、夕方以降に脳の松果体という部分で生成される睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となります。
深く眠るためには、メラトニンが十分に分泌されなければなりません。
また、セロトニンは睡眠・覚醒レベルの調節や自律神経の調節も行っているため、分泌量が低下すると良い睡眠がとれなくなり、昼夜に順応した覚醒レベルが調整できなくなります(※)。
ストレスがたまったり、生活リズムが乱れてセロトニンの分泌量が減少すると、以下のような変化が表れることが分かっています。
セロトニンの分泌量減少で起こる変化
・身体的には顔面の筋緊張低下によって顔のしまりがなくなる
・背中が丸くなる
・気分が滅入る
・ストレスによってイライラ感や攻撃性、衝動性が高まる
※:小西正良, and 吉田愛実. "セロトニン分泌に影響を及ぼす生活習慣と環境." 大阪河崎リハビリテーション大学紀要,(5) (2011): 11-20.
セロトニン不足でぐっすり眠れない人急増中?簡単に眠りの質を高めるコツとは? >>詳しく見る
深い睡眠がもたらす代表的なメリット4つ!

深い睡眠が心身にもたらす好影響には、以下のようなものがあります。
メラトニンを多量に分泌
深い睡眠(ノンレム睡眠)へスムーズに入眠できると、メラトニンが多量に分泌されます。
メラトニンには、強い抗酸化作用や成長ホルモンの分泌を促す作用があります。
「よく寝た」と実感できるような睡眠では、このメラトニンがスムーズに分泌されるのです。
女性ホルモンのエストロゲンが増えて美容効果も
メラトニンの分泌が増えるのに伴い、女性ホルモンの1つである「エストロゲン」も多く分泌されます。
そのため、深く眠れた日の朝は肌や髪もツヤツヤに。
逆に、睡眠不足が続くとエストロゲンの分泌が減って肌荒れの原因となります。
肥満を予防する
寝不足が続くと食欲をつかさどるホルモン「レプチン」の分泌量が低下し、逆に食欲を増加させるホルモン「グレリン」が多く分泌されます。
睡眠不足によって分泌されたグレリンによる食欲には、糖分や脂肪分が多い高カロリーな食べ物への欲求が高まるという特徴があるため、太りやすくなるのです。
逆に、深い眠りは糖代謝などを正常に保つ効果があるため、肥満予防になると言われています。
こころの健康を保つ
ストレスを感じると、副腎皮質ホルモン「コルチゾール」が多量に分泌されます。
コルチゾールは体の機能を保つために欠かせないホルモンですが、ストレスが慢性化すると分泌過剰になり、健康に悪影響を与えます。
睡眠不足が続くとコルチゾールが増え、ストレスが蓄積しうつ病などを引き起こす可能性が上昇するのです。
厚生労働省 e-ヘルスネット
「睡眠と生活習慣病との深い関係」
浅い眠りを改善して、深い眠りにつく方法
浅い眠りを改善し深い睡眠ノンレム睡眠の割合を増やすコツは、体内時計と自律神経を整えるとともに、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となるセロトニンの分泌量を増やすことです。
朝起きてすぐに太陽の光を浴びる
セロトニンは、朝日を浴びると活発に分泌されるようになります。
朝の日光には乱れた体内時計をリセットする効果もあるため、起床したらまずカーテンを開けて太陽光をとり入れましょう。
人は、朝に太陽光を浴びてから約15時間後に眠くなるようになっています。
朝の散歩は適度な運動にもなって、気持ちもリフレッシュします。
散歩の時間は、15分程度でも効果大!
習慣化して、セロトニンの分泌を促しましょう。

歩行や咀嚼は一定のリズムを意識する
一定のリズムで行う運動はセロトニンの生成を活性化します。
歩く時や歯磨きする時、咀嚼する時などは同じリズムをキープすることを意識してみましょう。
朝食・昼食・夕食は毎日同じ時間に食べる
規則的な毎日を送ることが、良質な眠りにつながります。
食事を毎日同じ時間に摂るようにすると体内リズムが一定になり、自律神経が整って睡眠の質も向上します。
休日も、できるだけ同じ時間帯に食事を摂ることに心掛けましょう。
また、昼食は正午~午後2時頃に摂るのがおすすめです。
この時間帯は、新しい脂肪細胞を作り出すタンパク質のBMAL1(ビーマルワン)の量が減るため、太りにくいと考えられています。

休日の前でも夜更かしはしない
平日と休日で就寝時間や起床時間が2時間以上ずれると、「ソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)」という体内時計のズレが生じます。
ソーシャルジェットラグによって体内リズムが乱れると、元に戻るまでに時間がかかります。
深く眠って睡眠の質を高めるためには、休日の前でも夜更かしはせず、生活リズムを大きく変えないことが大切です。
入浴の時はぬるめのお湯に浸かる
寝る2~3時間前に38℃前後のぬるめのお湯に約30分間浸かると、深部体温(内臓の温度)が0.5℃程度上昇します。
入浴後、この深部体温が低下していく途中で眠気が起こり、スムーズな入眠につながります。
そのため、深く眠るためにはシャワーではなく湯船に浸かった方が効果的です。
お風呂場のライトを暖色系にしたり、入浴剤をリラックス効果が高いラベンダーの香りなどにすると、さらに安眠効果が得られるでしょう。

睡眠環境を快適に整える
寝室の温度や湿度、明るさ、騒音、寝具も眠りを浅くする要因となります。
中でも、寝具と人体と間にできる空間の温湿度を指す「寝床内気候」は睡眠の質に大きな影響を与える要素です。
寝床内気候の快適な範囲は32℃前後、湿度は50%前後とされています(※1)。
柑橘系のエッセンシャルオイルの香りを嗅ぐ
使用する精油の種類によって、様々な効果が期待できるアロマテラピー。
エッセンシャルオイルの中には、リラックス感を高めたり、ストレスを緩和したりといった作用をもたらす精油もあります。
ある実験では、オレンジスイート精油に多く含まれる成分・リモネンがセロトニンの分泌量を増加させることが示唆される結果が出ました。(※2)。
また、別の実験結果では、レモンオイルが抗不安作用や抗うつ薬のような作用を有していることが示唆されています(※3)。

※1:水野一枝. "環境温湿度と睡眠." 睡眠口腔医学 2.2 (2016): 89-93.
※2:惠良友彦, et al. "抑うつ状態に対するアロマセラピーを用いた介入研究の現状と課題." 福岡県立大学看護学研究紀要 17 (2020): 5-15.
セロトニンを増やす効果がある「睡眠サプリ」を活用する
生活習慣や食生活の見直しといった手間をかけず深く眠れるようになりたい人には、睡眠の質を高める成分が配合されたサプリメントの活用もおすすめです。
睡眠薬とは異なり依存性もなく、ゆるやかに深い眠りへと導いてくれるでしょう。

セロトニンを増やす「ラフマ」とストレスを軽減させる「GABA」で、眠りの質を高める睡眠サプリ >>詳しく見る
深い睡眠で疲れをとって快適な毎日を過ごしましょう

今回は、深く眠る方法や眠りが浅くなる理由などについて、解説しました。
夜中に目が覚めることが増えたり、イライラすることが多くなったり、体重増加が気になっている人は、深く眠れていないかもしれません。
眠りが浅くなっていないか、チェックしてみてください。
深い睡眠で心身をしっかり休ませて、疲れが残らないスッキリとした朝を迎えましょう!