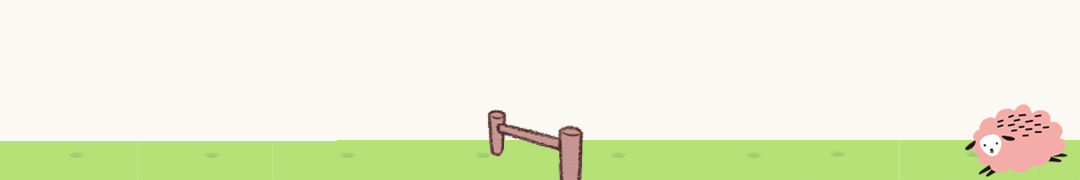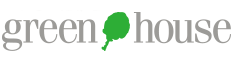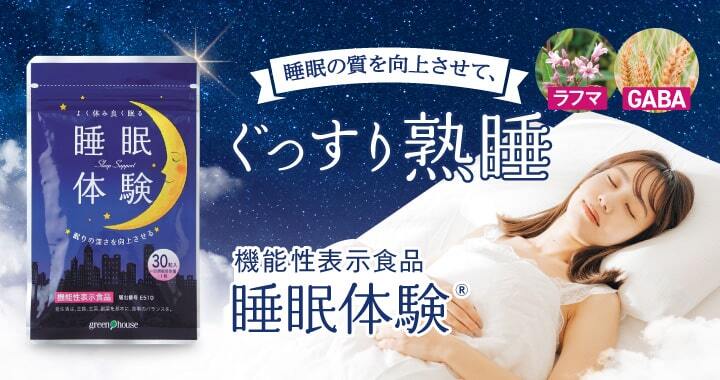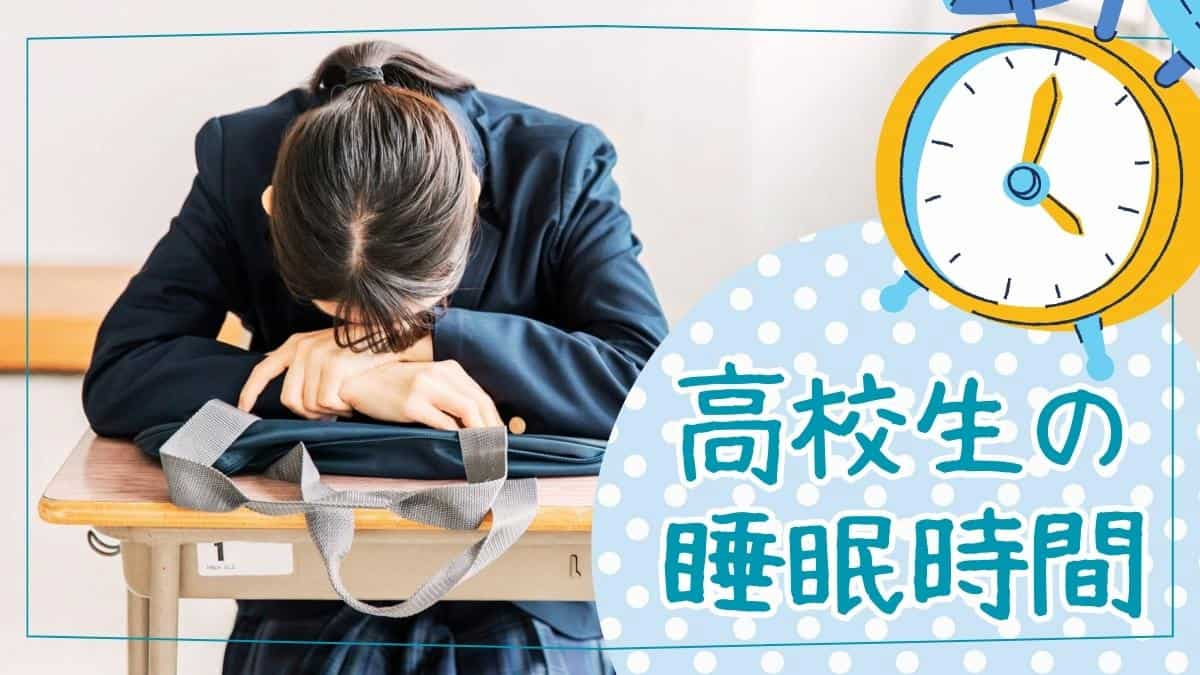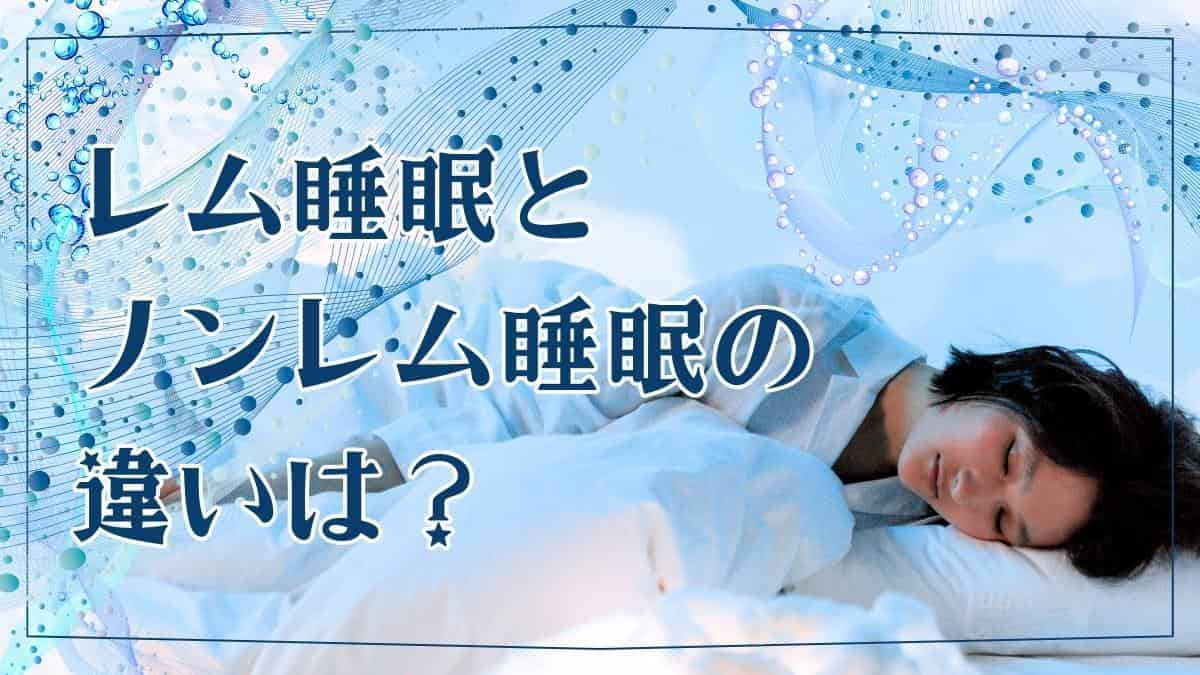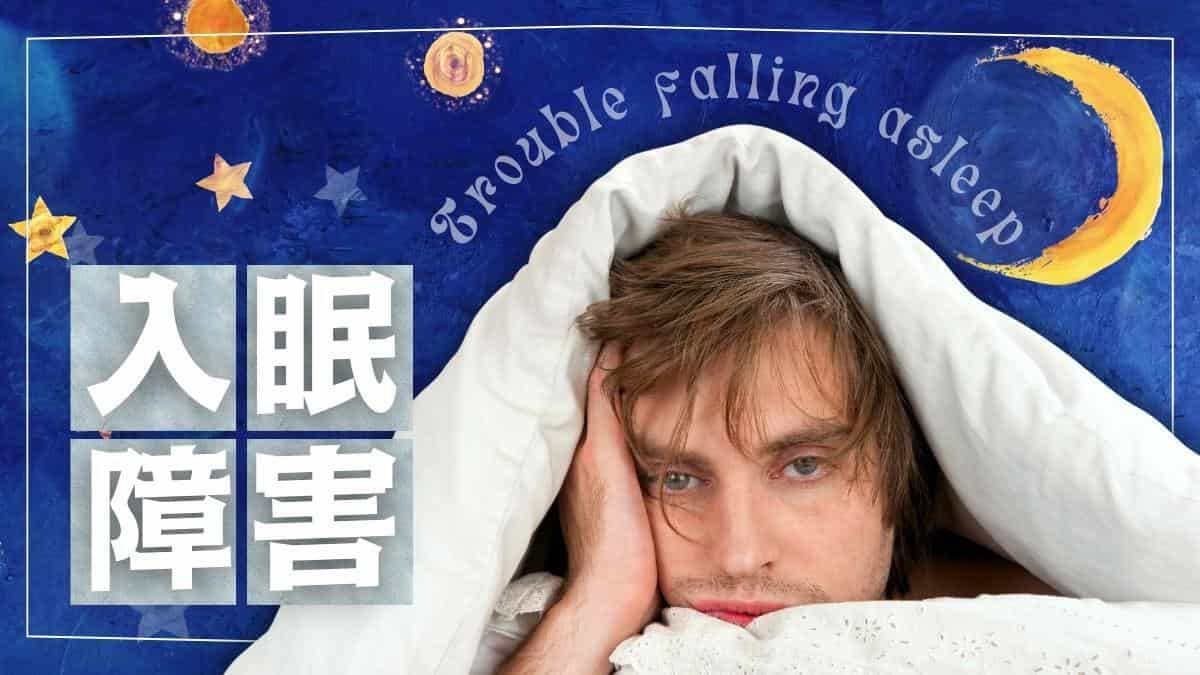中学生の平均睡眠時間は?13歳は何時に寝るのが理想?学力と睡眠の深い関係を解説
最終更新日:2025.11.26

中学生の子どもが夜遅くまで起きていることに、不安を感じたことはありませんか?
「うちの子、睡眠時間が少ないけど大丈夫?」「13歳って何時間寝ればいいの?」。
そんな疑問を抱える保護者の方は多いはずです。
この記事では、「中学生 睡眠時間」「13歳 何時に寝る」などで検索する親世代・本人に向けて、平均睡眠時間の実態から理想の就寝時間、学力や成長への影響、すぐに取り組める睡眠改善法まで、わかりやすく解説します。

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
睡眠栄養指導士
小田 健史
健康食品業界で数々の商品開発や販促に12年以上携わる。
睡眠不足に悩まされ続けた自身の不眠体験から、一念発起して「睡眠栄養指導士」の資格を取得し、自らの知識と経験を基に機能性表示食品に登録された睡眠向上サプリ「睡眠体験」を開発。
現在、睡眠栄養指導士として多くの悩める方々へ睡眠の改善に関する情報を発信中!
<資格>
・一般社団法人 睡眠栄養指導士協会
睡眠栄養指導士® 中級
パーソナル睡眠アドバイザー®
・特定非営利活動法人 日本成人病予防協会
健康管理士 一般指導員
目次
中学生の平均睡眠時間は?今どきの子どもは何時間寝ているのか
スマホや塾通い、部活動に忙しい中学生たち。
あなたのお子さんは、毎日どのくらい寝ていますか?
実は日本の中学生の多くが「慢性的な睡眠不足」に陥っており、それが集中力や情緒、さらには学力低下に直結していると指摘されています。
このセクションでは、実際の平均睡眠時間のデータをもとに、現在の中学生が置かれている“眠れない現実”と、その背景にある問題を解き明かします。
平均睡眠時間は7時間程度という実態
総務省が行った「令和3年社会生活基本調査」の結果を基に算出した中学生の平均睡眠時間は、7時間30分程度です。
これは、本来必要とされる時間よりも明らかに短い水準です。
| 中学生の平均就寝・起床時間 | |||
|---|---|---|---|
| 平均就寝時間 | 平均起床時間 | ||
| 平日 | 23時12分 | 6時45分 | |
| 土曜日 | 23時16分 | 7時46分 | |
| 日曜日 | 23時01分 | 7時59分 | |
※「令和3年社会生活基本調査」を基に作成
中学生は、体の成長と脳の発達が著しい時期。
米国睡眠医学会は、13歳~18歳の青少年は8~10時間の睡眠をとるように推奨しています。
つまり、多くの子どもが日常的に睡眠不足の状態にあるのです。

13歳は何時に寝るのが理想?成長ホルモンが出る就寝タイミングとは
「もう中学生だから、少しくらい夜更かししても大丈夫」。本当にそうでしょうか?
13歳前後の中学生は、身体と脳が同時に発達する“人生で最も重要な時期”にあります。
この時期の睡眠は、単なる休息ではなく「心と体の成長を支えるスイッチ」の役割を果たしています。
このセクションでは、成長ホルモンの分泌リズムや思春期特有の睡眠特性をもとに、13歳に最適な「寝る時間」とその根拠を詳しく解説します。
「睡眠時間」だけでなく「寝始めの時間」が重要
13歳の子どもにとって、ただ長く寝るだけでは十分とは言えません。
特に重要なのは、どの時間帯に眠り始めるかという「就寝時間」の方です。
成長ホルモンの分泌は、「入眠から約1〜2時間後の深い睡眠中」にピークを迎えますが、この分泌は22時〜深夜2時ごろに集中していることが分かっています。
つまり、夜遅くに寝てしまうと、このホルモンが十分に分泌されず、「寝てはいるのに成長しにくい」という状態になってしまうのです。

理想的な就寝時間は「21時半〜22時」
13歳の平均的な起床時間は、通学時間を考えると 朝6時半〜7時前後。
そこから逆算して、理想の睡眠時間が8〜9時間だとすると、21時半〜22時までに寝ることが、心身の発達にもっとも適したリズムと言えます。
ただし、現実的には塾や部活などで帰宅が遅くなることもあるでしょう。
その場合でも、遅くとも22時半〜23時には入眠できるよう、スマホやゲームの使用を調整するなど、生活習慣の工夫が必要です。

「寝る前スマホ」で成長ホルモンの分泌が阻害される?
13歳という年齢はメラトニン(眠気を促すホルモン)の分泌リズムが不安定になる時期でもあります。
ここにスマホやタブレットのブルーライトが加わると、メラトニンの分泌が大きく抑制され、「眠くならない」「布団に入っても眠れない」状態に。
このまま入眠が遅れれば、当然、成長ホルモンの分泌タイミングともズレが生じます。
つまり「夜スマホ」は、思春期の子どもにとって二重の意味で睡眠の質を損なう大敵なのです。
メラトニンで睡眠リズムを整える!中学生の眠りを改善する睡眠サプリ >> 詳しく見る
なぜ中学生の睡眠時間は削られてしまうのか?スマホ・塾・部活のリアル
中学生の睡眠時間が短くなってしまう背景には、以下のような“この年代ならでは”の事情があります。
1. 塾・部活・習い事で帰宅時間が遅い
中学生になると、塾や習い事に通い始める子どもが増え始めます。
さらに部活動も合わせると、帰宅が21時を超えるケースは珍しくありません。
夕食や入浴、宿題に追われ、気づけば深夜という生活が常態化しています。
2. SNS・動画・スマホゲームが「やめられない」
思春期の子どもたちは、友人関係の多くをSNSで維持しています。
「LINEが来たらすぐに返さなきゃ」「クラスのグループチャットを見逃せない」といったプレッシャーが、就寝直前までスマホを手放せない要因になっています。
その結果、就寝時刻になっても脳が覚醒したままとなり、布団に入ってもなかなか寝つけないケースが増加しています。

3. 思春期による体内時計の後退(睡眠相後退症候群)
思春期は、「メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌量が大幅に減少する」といった生理的変化が起きます。
メラトニンの分泌量は幼少期にピークに達し、加齢とともに減少。
特に、思春期は著しく分泌量が低下し、概日リズム(体内時計)に変化を及ぼす可能性があります(※1)。
これは自然現象であり、夜型になりやすい一因ですが、学校の開始時間は変わらないため、結果的に“夜型睡眠・早朝起床”という不自然な状態が続き、慢性的な睡眠不足に陥りやすくなるのです。

4. 宿題やテスト勉強のプレッシャー
中学に進学すると、定期テストや受験が視野に入り、勉強時間が長くなります。
「勉強しなければいけない」という義務感が、脳の緊張状態を高め、睡眠の質を下げる原因にもなります。
睡眠と学力の関係は?記憶力アップと脳のコンディションの密接なつながり
「よく寝る子は頭がいい」と言うと少し極端に聞こえるかもしれませんが、近年の研究では中学生の睡眠時間と学力・集中力に明確な相関があることが示されています。
脳は「寝ている間に記憶を整理している」
中学生は毎日、大量の情報をインプットしています。
授業内容、テスト勉強、部活の作戦、人間関係…。
こうした情報は脳内に「短期記憶」として一時保存された状態ですが、これを「長期記憶」に移す作業が、睡眠中に行われるのです。
特に、深いノンレム睡眠の時間帯には「海馬→大脳皮質」への記憶の固定作業が活性化します。
この時間帯に質の高い睡眠が取れていなければ、せっかく勉強しても記憶に残りにくい状態になってしまいます。
| レム睡眠とノンレム睡眠の違い | |||
|---|---|---|---|
| 睡眠の種類 | 特徴 | ||
| ノンレム睡眠 | 徐波睡眠とも呼ばれる深い眠り。眠りの深さには4段階あり、第3または4段階目の深いノンレム睡眠は入眠後2時間以内に表れる。ノンレム睡眠時に起床すると目覚めが悪い。 | ||
| レム睡眠 | 急速な眼球運動があるのが特徴で、覚醒状態あるいはノンレム睡眠の第1段階と同じような睡眠状態。夢を見ることが多い。レム睡眠のタイミングで起きると目覚めが良くなる。 | ||
睡眠不足の中学生は「ぼーっとする」「ミスが多い」
慢性的な寝不足が続くと、脳は疲れをリセットできません。
その結果、以下のような状態が日常的に見られるようになります。
・朝からぼーっとしていて授業に集中できない
・テストでケアレスミスが多い
・急にイライラする、感情の起伏が激しくなる
・暗記が苦手になる、記憶が定着しにくい
特に思春期の脳は感情のコントロールにも関与するため、睡眠不足はメンタルバランスにも影響を及ぼします。
たかが睡眠、されど睡眠。学力や集中力を伸ばすうえで、実は最も費用対効果の高い自己投資が「よく眠ること」なのです。

中学生でも手軽に始められる改善方法はこちら >> 詳しく見る
子どもの睡眠の質を高めるために、親ができるサポート
13歳にもなると、自分で寝る時間を決めたがる子も多くなりますが、まだ自己管理が十分にできない時期です。
そのため、以下のような家庭全体での睡眠サポートが極めて重要になります。
・21時以降はスマホをリビングに置く「夜のルール」をつくる
・夕食、入浴、宿題などをなるべく毎日同じ時間に行い、リズムを整える
・朝は7時までにカーテンを開け、日光を浴びさせて体内時計をリセットする
・寝室を暗く静かに保ち、睡眠に適した環境を用意する
また、「寝つきが悪い」「すぐ目が覚める」といった悩みが続く場合は、食生活の見直しや、手軽に取り入れられる睡眠サポート習慣を検討してみるのも一つの方法です。
まとめ | 中学生の就寝時間は22時前が理想。親ができる見直しとは?
中学生の睡眠は、単なる「疲労回復」のためだけでなく、心身の成長、学力の向上、情緒の安定に密接に関わっています。
特に13歳前後は、成長ホルモンが活発に分泌されるタイミング。
この「成長のゴールデンタイム」を逃さないためには、21時半〜22時までに寝る生活リズムを整えることが非常に重要です。
しかし、部活や塾、スマホ習慣などで夜型化が進みがちなこの時期、理想のリズムに戻すのは簡単ではありません。
そんなときは、家庭全体でのサポートや生活習慣の見直しに加えて、睡眠の質を自然に整える工夫も有効です。
最近では、無理な制限をかけずに「眠りやすい状態」をサポートする方法を取り入れる家庭が増えています。
たとえば、睡眠サポートサプリは、子どもが自然に眠りに入りやすくなる手助けとして活用できます。
親ができる見守りと合わせて取り入れることで、「すんなり眠れる」「朝すっきり起きられる」状態をサポートし、学びと成長を支える大きな土台になります。
まずは生活習慣の見直しと合わせて、手軽に取り入れられるサプリを試してみるのもひとつの方法です。
よくある質問
睡眠サポートサプリメントの詳細はこちら