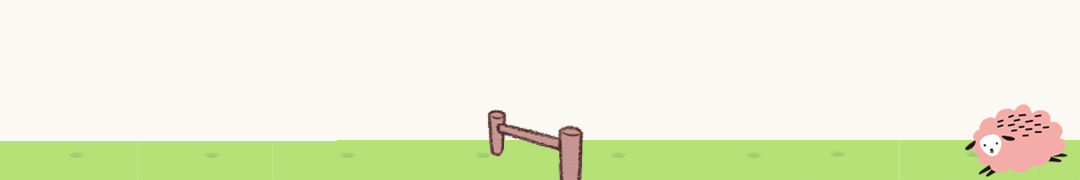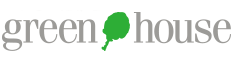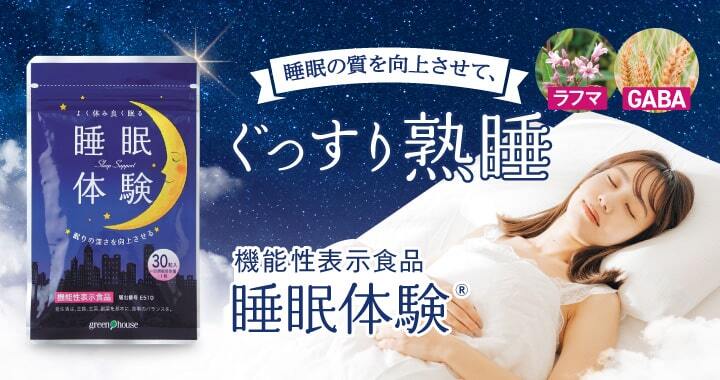寝すぎて気持ち悪い・頭が痛い原因と対処法|吐き気や体調不良の予防策も解説
最終更新日:2025.11.26

「休みの日にたっぷり寝たのに、なぜか気持ち悪い」「寝すぎたら頭痛がして起きるのがつらい」。
そんな経験はありませんか?
寝不足による体調不良はよく知られていますが、実は“寝すぎ”も体に悪影響を及ぼすことがあります。
この記事では、「寝すぎて気持ち悪い」「寝すぎて頭が痛い」といった不調の原因や、その対処法・予防法について、分かりやすく解説します。
さらに、睡眠の質を改善するための生活習慣や、睡眠サポートサプリメントの活用方法についてもご紹介します。

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
睡眠栄養指導士
小田 健史
健康食品業界で数々の商品開発や販促に12年以上携わる。
睡眠不足に悩まされ続けた自身の不眠体験から、一念発起して「睡眠栄養指導士」の資格を取得し、自らの知識と経験を基に機能性表示食品に登録された睡眠向上サプリ「睡眠体験」を開発。
現在、睡眠栄養指導士として多くの悩める方々へ睡眠の改善に関する情報を発信中!
<資格>
・一般社団法人 睡眠栄養指導士協会
睡眠栄養指導士® 中級
パーソナル睡眠アドバイザー®
・特定非営利活動法人 日本成人病予防協会
健康管理士 一般指導員
目次
寝すぎると体調不良になるのはなぜ?
日頃の寝不足を解消するためにたっぷり寝たのに、かえって気持ちが悪くなってしまった…。
そんな寝すぎによって起こる不調のメカニズムを、自律神経やホルモンバランス、脳の働きなどの観点から解説します。
正しい知識を得ることで、繰り返す不調の対策が見えてきます。

1.自律神経が乱れてしまう
寝すぎると交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、自律神経の乱れが生じます。
本来、朝起きたときには交感神経が優位になって体を活動モードに切り替えますが、長時間眠ってしまうとその切り替えがうまくいかず、頭痛・吐き気・めまい・倦怠感などの症状が出やすくなります。
2.血糖値やホルモンバランスの変動
長時間の睡眠により食事間隔が空くと、血糖値が下がりすぎて低血糖状態になり、気分の悪さや吐き気、集中力の低下を引き起こすことも。
また、睡眠ホルモンである「メラトニン」や覚醒を促す「コルチゾール」の分泌リズムも乱れ、体内時計が狂ってしまいます。
3.ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)
休日に寝すぎて生活リズムがずれると、平日との睡眠サイクルの差が生じ、時差ボケのような症状が出ることがあります。
これを「ソーシャル・ジェットラグ」と呼び、頭痛や吐き気、疲労感の原因になります。
寝すぎによる頭痛のメカニズムとは?
「寝すぎて頭が痛い」と感じる原因にはいくつかのパターンがあります。
片頭痛タイプ
寝すぎると、脳内の神経伝達物質「セロトニン」の分泌が急激に変動し、血管の拡張が起きることがあります。これが片頭痛の原因です。
片頭痛の症状は、ズキズキと拍動するような痛みが特徴で、光や音に過敏になることもあります。
緊張型頭痛タイプ
長時間同じ姿勢で寝ていたり、枕が合っていなかったりすると、首や肩に負担がかかり、筋肉が硬直して緊張型頭痛が起こります。
こちらは締めつけられるような痛みで、特に後頭部から首筋にかけて重だるさを感じます。

脳への酸素供給不足
寝すぎによって呼吸が浅くなり、酸素が十分に供給されなくなると、軽い酸欠状態になり頭痛やめまいを引き起こすことがあります。
睡眠リズムを整えて不調を改善!対策方法がこちら >> 詳しく見る
寝すぎによる吐き気の原因と対処法
吐き気は、自律神経の乱れや血糖値の低下が引き金になって引き起こされるケースが少なくありません。
特に朝食を抜いたまま午前中を過ごすと、空腹による低血糖が悪化して吐き気が強くなるケースがあります。
吐き気を和らげる対処法
1.レモン水や炭酸水を飲む
胃のむかつきを軽減し、吐き気をやわらげます。

2.内関(ないかん)のツボを押す
手首の内側にある「内関」は、乗り物酔いなどに効果的な吐き気対策のツボです。
手のひらを上に向けた状態で、手を握り締めた時に出る2本の腱の間と、手首のシワから指3本分離れた場所の交差する点をゆっくり指圧しましょう。

3.軽いストレッチや深呼吸を行う
自律神経を整える効果があります。
寝すぎの対処法と予防策
寝すぎて起きたときの気持ち悪さや頭痛にどう対処すればいいのか迷っていませんか?
ここでは、今すぐできる寝すぎのリセット法と、再発を防ぐための生活習慣の整え方を具体的に紹介します。

1.適切な睡眠時間を守る
理想的な睡眠時間は成人で6~8時間。休日でも平日と1時間以上差が出ないよう心がけましょう。
「睡眠不足を取り返そう」と思って寝すぎるより、毎日の睡眠の質を安定させることの方がはるかに重要です。
2.起床時間を固定する
就寝時間が多少前後しても、「起きる時間」はできるだけ毎日一定にすることで体内時計が安定し、朝スッキリ目覚めやすくなります。
3.起きたら朝日を浴びる
起床後すぐにカーテンを開け、自然光を浴びることでメラトニンの分泌が止まり、体内リズムがリセットされます。
朝日を浴びる習慣は、寝すぎによる自律神経の乱れを防ぐ助けになります。
睡眠の質を高めるためのポイント
「睡眠時間は足りているのに、疲れが取れない」「寝すぎてしまって体調が悪い」。
そんな悩みを持つ方は、睡眠の“量”よりも“質”に注目すべきです。
睡眠の質を向上させるためには、以下のようなポイントが重要です。
◆ 寝る前にスマホを見ない
ブルーライトが睡眠ホルモンに影響を与えるため、寝る1時間前にはスマホをお休みしましょう。
◆ 寝室の温度や湿度を整える
快適な眠りには適温(18~22℃)と湿度(40~60%)を保つことが重要です。
◆ リラックスできる習慣(アロマ、入浴)を取り入れる
アロマオイルやぬるめのお風呂で心と体をリラックスさせ、睡眠の質を向上させましょう。
まとめ | 寝すぎを防ぐには、量より質の睡眠を
寝すぎは一見、健康的なように思えて実は体調不良の原因になることがあります。
頭痛や吐き気の背後には、自律神経の乱れやホルモンバランスの崩れ、生活リズムの乱れが潜んでいます。
大切なのは「長く眠ること」ではなく、「質の良い睡眠をとること」。
自分の生活習慣を見直し、必要に応じて睡眠の質を高める工夫を取り入れることで、寝すぎによる不調を防ぎ、心身ともにすっきりとした毎日を送ることができるでしょう。
睡眠の質を高めるための生活習慣や食生活の実践に加えて、良質な眠りをサポートする睡眠サプリの活用もおすすめです。
自分に合う方法で寝すぎによる吐き気や頭痛を予防して、快適な毎日を送りましょう。
睡眠の質を高めたい人は必見!日本初の睡眠サプリがこちら >> 詳しく見る
よくある質問
睡眠サポートサプリメントの詳細はこちら