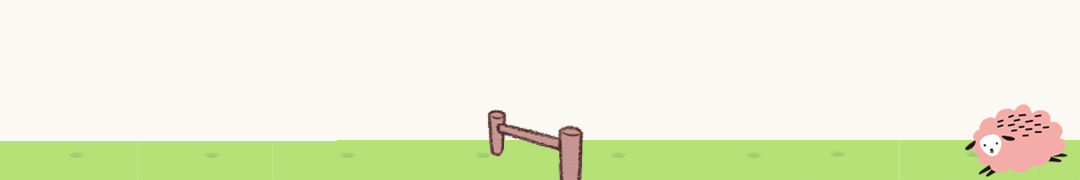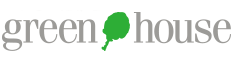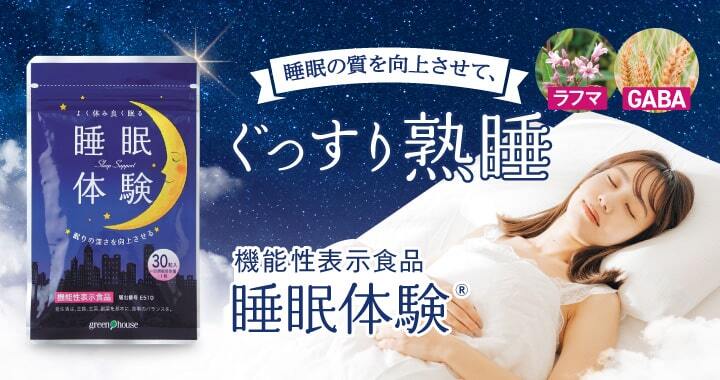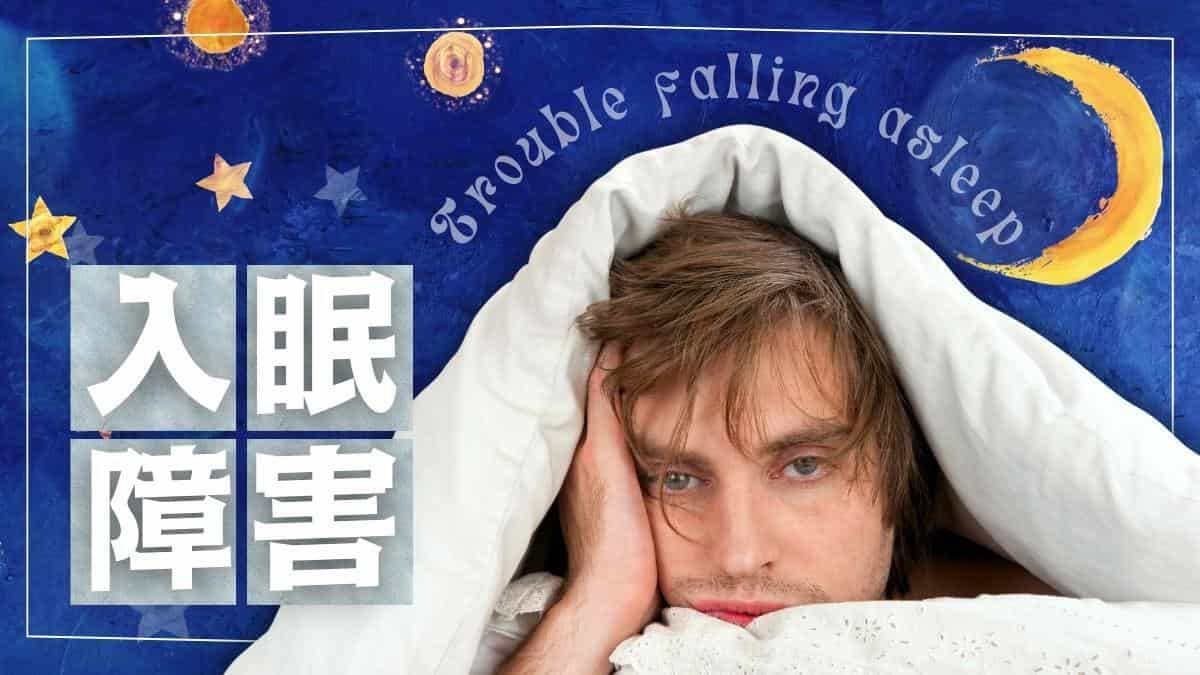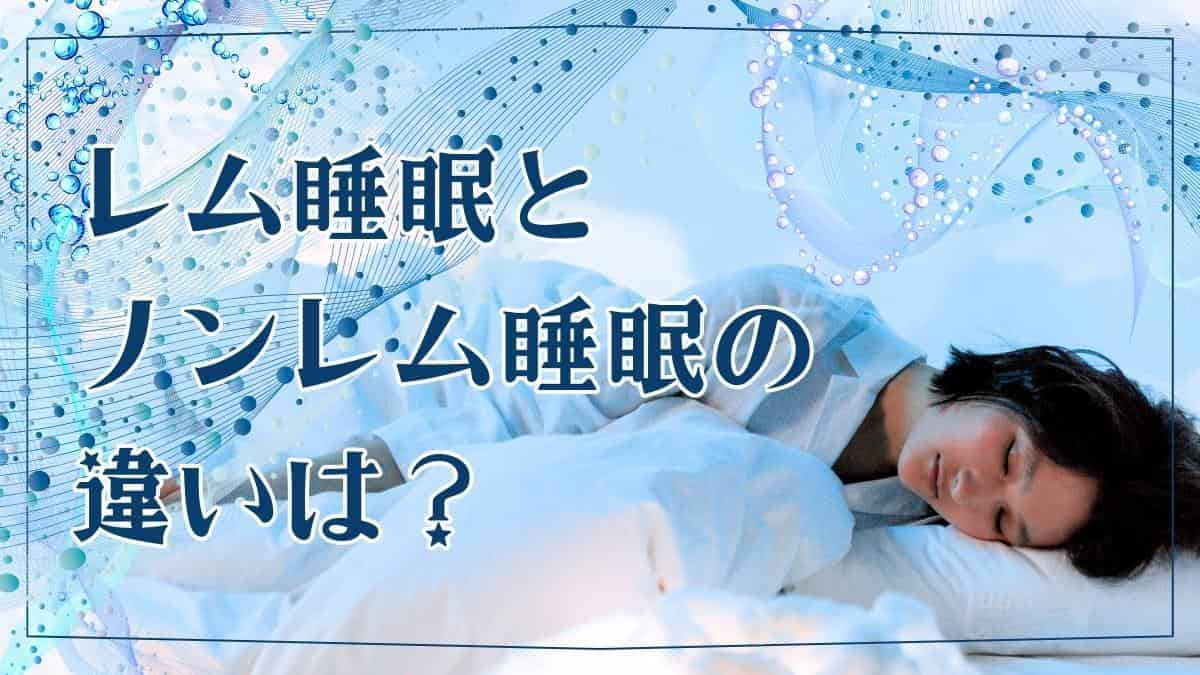早朝覚醒の原因と対策|朝早く目が覚めて二度寝できない人へ、自然な眠りの整え方
最終更新日:2025.05.15

「まだ5時前なのに目が覚めた…」「二度寝できないまま、布団の中で時間を持て余す」。
こうした“アラームより早く何時間も早く目が覚めてしまう”悩みを抱えていませんか?
これはいわゆる「早朝覚醒」と呼ばれる現象で、以前は高齢者に多い睡眠トラブルとされていましたが、最近では20代〜30代といった若年層にも広がっています。
本記事では、早朝覚醒の代表的な原因と、その対策法をわかりやすく解説します。
さらに、再び快適な睡眠を手に入れるための工夫や、近年注目されているサポートアイテムもご紹介します。

この記事の執筆者
グリーンハウス株式会社
睡眠栄養指導士
小田 健史
健康食品業界で数々の商品開発や販促に12年以上携わる。
睡眠不足に悩まされ続けた自身の不眠体験から、一念発起して「睡眠栄養指導士」の資格を取得し、自らの知識と経験を基に機能性表示食品に登録された睡眠向上サプリ「睡眠体験」を開発。
現在、睡眠栄養指導士として多くの悩める方々へ睡眠の改善に関する情報を発信中!
<資格>
・一般社団法人 睡眠栄養指導士協会
睡眠栄養指導士® 中級
パーソナル睡眠アドバイザー®
・特定非営利活動法人 日本成人病予防協会
健康管理士 一般指導員
目次
そもそも「早朝覚醒」とは?どんな症状がある?
睡眠トラブルにはさまざまな種類がありますが、「早朝覚醒」は以下のような特徴を持ちます。
早朝覚醒の特徴
・起床予定時刻より2時間以上早く目が覚めてしまう
・起床時刻までまだ時間があるのに再び眠れない
睡眠時間が短くなることで、日中の集中力低下や疲労感、情緒不安定といった悪影響も及ぼします。
一見地味なトラブルですが、放っておくと生活全体に支障をきたすため、早めの対策が肝心です。

なぜ早朝に目が覚めるの?早く起きてしまう主な原因とは
「なぜ自分は毎朝こんなに早く目が覚めてしまうのか」と悩む方は少なくありません。
早朝覚醒の原因は一つではなく、以下のような要因が複雑に絡んでいます。
1. 加齢による体内時計の変化
年齢を重ねると、体内時計(概日リズム)が前倒しになりやすくなります。
特に40代以降は深部体温の下降が早まり、早朝に自然と目が覚める傾向が強まります。
また、年齢とともにメラトニンの分泌量が減少し、自然と早寝早起き傾向になります。
その結果、まだ夜明け前でも目が覚めてしまうのです。
ただし、20代や30代でも生活習慣やストレスの影響で同様の変化が起きることもあります。
2. ストレス・不安による自律神経の乱れ
人はストレスを感じると交感神経が優位になり、リラックス状態をつかさどる副交感神経が働きにくくなります。
その結果、睡眠が浅くなったり、本来眠っている時間に脳が覚醒方向に傾いてしまったりすることがあります。
さらに、ストレスを受けた脳は、コルチゾール(覚醒ホルモン)を活発に分泌する傾向に。
これにより、眠っていても浅い睡眠が続き、わずかな刺激でも目覚めやすくなるのです。

3. 生活習慣の乱れ
夜遅くまでスマホを見る、寝る直前にカフェインやアルコールを摂取するなど、睡眠を妨げる習慣も早朝覚醒の原因になります。
特に、寝つきが良いのに朝が早すぎる人は、体内リズムが乱れているサインかもしれません。
4. うつ状態の初期症状
早朝覚醒は、うつ病や軽度の気分障害の初期症状としても知られています。
以下の傾向がある場合は注意が必要です。
早朝覚醒で注意が必要な場合
・早朝に目が覚めてしまう日が2週間以上続いている
・再び寝ようとしても不安や焦燥感で眠れない
・食欲低下や気分の落ち込みも同時にある
このようなケースでは、睡眠薬やサプリメントの使用だけでなく、精神科や心療内科での相談が必要です。

ぐっすり眠れない人急増中?それはセロトニン不足が原因かも… >>詳しく見る
二度寝できないのはなぜ?そのメカニズムと対処法
朝、早く目が覚めたあとに「もう一度寝たいのに眠れない…」と感じるのは非常にもどかしいものです。
この現象には、単なる睡眠不足以上に、脳と体の調整メカニズムが関係しています。
ここでは、二度寝ができない4つの理由を詳しく見ていきましょう。
1. 覚醒ホルモンのピーク分泌と覚醒維持メカニズム
目覚める直前から、脳内のノルアドレナリンやコルチゾールといったストレス反応に関わるホルモンが急増します。
これらは交感神経を活性化させ、心拍数や血圧を上げて身体を「起きる準備モード」に入れます。
このホルモン分泌のピークは、目覚め後数時間持続するため、二度寝しようとしても脳が強い覚醒状態を維持してしまい、再度の深い睡眠に入ることを阻みます。

2. 体内時計(サーカディアンリズム)による覚醒促進
私たちの体内時計は24時間周期でホルモン分泌や体温調整を行い、朝に自然と目が覚めるようにセットされています。
特にメラトニン(睡眠ホルモン)は夜間に分泌が増え、朝に急激に減少します。
朝のメラトニン低下は覚醒を促す信号となり、これが体内時計により制御されているため、たとえ二度寝を試みても体は「起きる時間」と認識してしまいます。
3. 睡眠の深さと覚醒のタイミング(睡眠段階の影響)
睡眠はレム睡眠とノンレム睡眠のサイクルで構成されていますが、早朝覚醒が起こると、浅い睡眠段階や覚醒状態に入りやすいタイミングに重なりやすいことがわかっています。
つまり、自然に目が覚めやすい睡眠の深さの段階にあるため、二度寝が困難になるのです。
4. ストレスや外的刺激による覚醒の増強
心理的ストレスや不安があると、コルチゾール分泌が増加。
これが過剰になると覚醒状態が強まり、睡眠の維持が難しくなります。
さらに、スマホのブルーライトやカフェイン摂取はメラトニンの分泌を阻害し、睡眠開始からの質を下げるだけでなく、朝の再入眠も妨げます。

早朝覚醒は“リズムの乱れ”が原因かも?日中から改善する3つの新習慣
早朝覚醒で「アラームより早く目が覚める」「二度寝できない」と悩んでいませんか?
実は、その原因は体内時計の乱れや生活習慣にあります。
そこで、ここでは早朝覚醒のメカニズムをわかりやすく解説し、今すぐ始められる生活習慣の改善方法を3つご紹介します。
質の良い睡眠を取り戻し、朝のストレスを減らすヒントをお届けします。
1. 夕方の過ごし方を見直して睡眠リズムを改善
早朝覚醒は体内時計の乱れが大きな原因です。
そこで注目したいのが、夕方の過ごし方。
夕方に適度な運動をしたり、適切な光の浴び方を実践したりすることで夜の睡眠が深くなります。
夕食は寝る3時間前までに済ませ、カフェインは午後3時以降控えましょう。
これで夜の眠りが安定し、早朝に目覚める回数が減ります。

2. スマホ断ちで脳をリラックスさせて二度寝を助ける
寝る前や早朝にスマホを使うと、ブルーライトで脳が覚醒し、二度寝が難しくなります。
寝る1時間前はスマホを控え、代わりに読書や音楽でリラックスを。
早朝に目が覚めてもスマホを触らず、深呼吸や軽いストレッチで眠気を呼び戻しましょう。
3. 朝型習慣を少し緩めて体内リズムを調整
毎朝同じ時間に起き続けることが、逆に早朝覚醒を強めることも。
週末に起床時間を少し遅らせる、朝は自然光をゆっくり浴びるなど、リズムの柔軟性を持つことが大切です。
朝の瞑想や軽い運動もストレス軽減に効果的です。
まとめ|早朝覚醒を根本から改善して朝までぐっすり
早朝覚醒は体内時計の乱れだけでなく、ストレスや生活リズムの乱れ、自律神経の不調も関係しています。
今回ご紹介した生活習慣の見直しは、体内リズムを整え、深い睡眠を取り戻すための基本的かつ重要な対策です。
しかし、日常生活の忙しさやストレスが続くと、自分だけの力では十分な改善が難しいケースも少なくありません。

そこで注目したいのが、睡眠サポートサプリの活用です。
良質な睡眠に欠かせない成分をバランスよく配合したサプリは、自律神経の働きをサポートし、寝つきや睡眠の質を向上させることが期待できます。
生活習慣の改善と組み合わせることで、早朝覚醒の症状をより効果的に和らげ、朝までぐっすり眠れる体質へと導きます。
早朝覚醒に悩んでいる方は、まずはできる範囲で生活習慣を見直しつつ、専門的なサポートとしてサプリメントを取り入れることを検討してみませんか。

質の良い睡眠は日中のパフォーマンス向上や心身の健康にも直結します。
自分に合った対策で、快適な朝を取り戻しましょう。
睡眠の質を高め、深いノンレム睡眠をしっかりとる方法 >>詳しく見る
よくある質問
加齢やストレス、体内時計の乱れなどが影響し、早朝に浅い眠りに入りやすくなります。特に20代でもストレスや生活リズムの乱れがあると、早く目が覚めやすくなることがあります。
早朝はコルチゾールという覚醒を促すホルモンが分泌される時間帯です。また、不安や緊張が残っていると交感神経が優位になり、再入眠が難しくなります。
いいえ、年齢にかかわらず生活習慣や精神的なストレスの影響で早朝覚醒は起こり得ます。特にスマホの使い過ぎや夜更かし、不規則な生活が影響することがあります。
はい。睡眠の質を整える成分を含んだサプリメントは、早朝覚醒の緩和や自然な再入眠をサポートします。生活習慣の見直しと併用することで、より高い効果が期待できます。
睡眠サポートサプリメントの詳細はこちら
睡眠の質の向上をサポート
おすすめ記事
睡眠サポートサプリメントの詳細はこちら